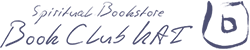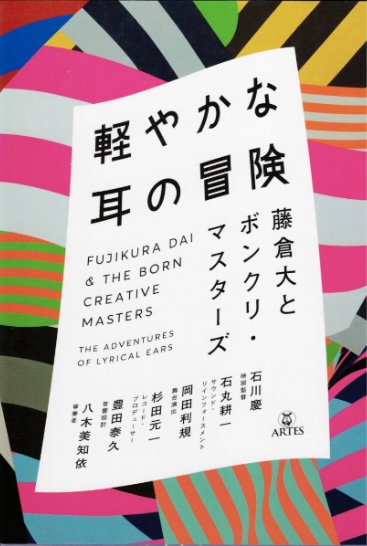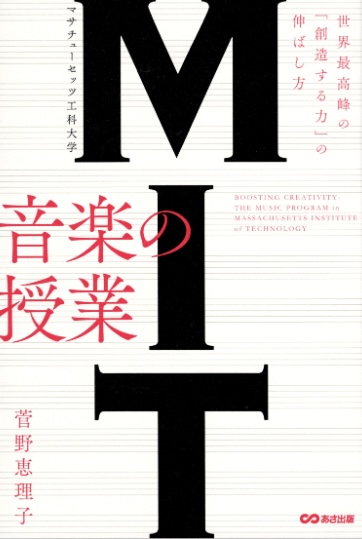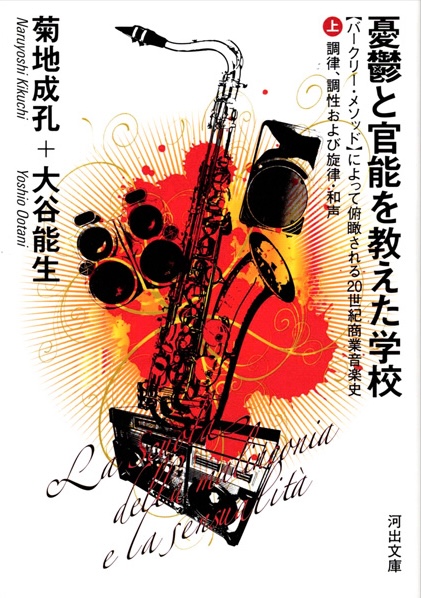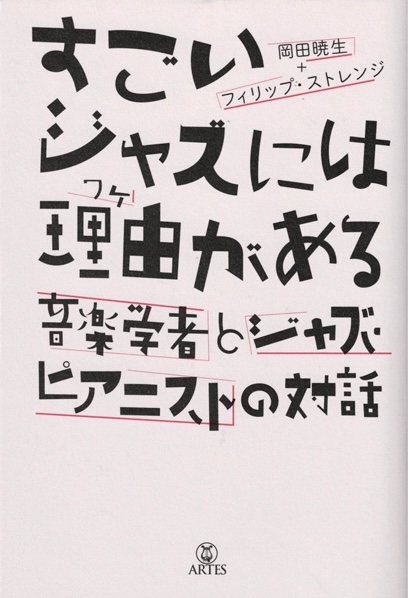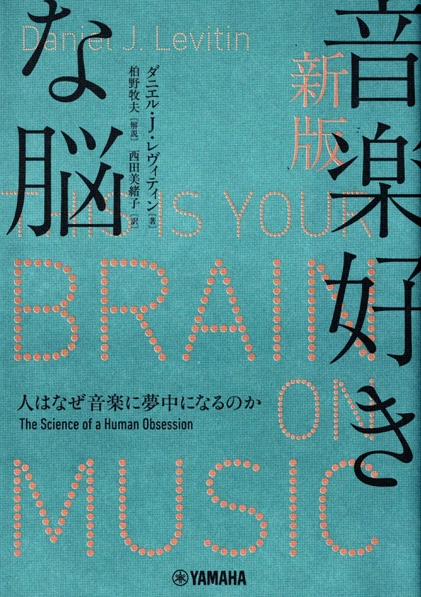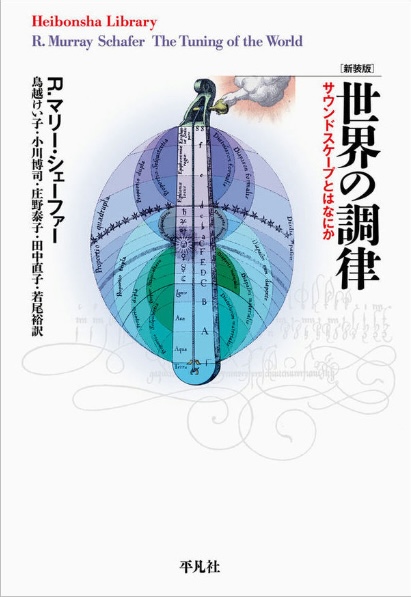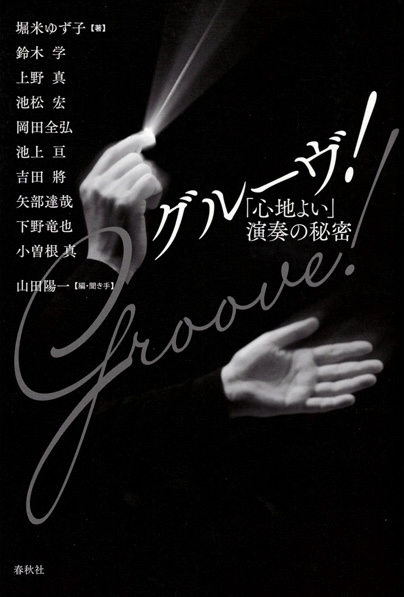2024年6月 満月のたより
楽しい音楽観察
音楽を聴く時、どうしてこんなにも心動かされるのか、
いったいこの曲の何が、自分のどこを刺激しているのか、
疑問に感じたことはありませんか?
普段私たちは音楽の、メロディー、ハーモニー、リズムなどの要素を、
一つのかたまりとしてとらえ、総合的に楽しむことが多いように思います。
ですが世の中には、思わぬ視点から音楽をとらえ、掘り下げている人もいるようで、
そういった人たちのアプローチは、日々の生活を送るうえでも、
思わぬ気付きをもたらすことがありそうです。
音楽に限らず、芸術や科学、社会経済、料理や洗濯、乗り物の運転など、
様々な行為や事象を、
自分なりの視点で分解、観察したのち、
アレンジを加えて再度組み立ててみる。
その時そこに、曰く言い難いあなたの気配が滲み出ていたら、
あなたは創造への一歩を踏み出したと言えるのかもしれません。
今回は、音楽を独自の視点で観察する本を集めてみました。
今日は6月の満月です。
今月も皆さまに、素敵な本との出会いをお届けできれば幸いです。
私たちは音楽を聴くことによって、音楽のジャンルや形式に関するスキーマを作り上げている。
何気なく耳に入ってきているだけでも、特に音楽を分析しようと思わなくてもいい。
ごく幼い頃から、人は自分の文化の音楽で決められた、正しい音の動きを知っている。
やがて生まれる音楽の好き嫌いは、たいていの場合、
子供の頃耳にした音楽によって出来上がった認知スキーマの種類で決まってくる。
ただし必ずしも、子供の頃聴く音楽によって人生を通した音楽の好みが決まってしまうという意味ではない。
– ダニエル・J・レヴィティン - 『新版 音楽好きな脳』より
書籍
[Art / 音楽]
軽やかな耳の冒険
藤倉大とボンクリ・マスターズ
藤倉大、八木美知依 他 / アルテスパブリッシング
2420円(税込)
人間はみな、生まれつきクリエイティヴだ(ボーン・クリエイティヴ)として、2017年から実施されているボーダレスな音楽祭。そのアーティスティック・ディレクターであり、作曲家である著者が、映画監督、演出家、音響デザイナーなど、様々な響きの匠たちに質問を投げかける。相手への尊敬と好奇心にあふれた対話は、読み手をワクワクとした音の冒険へと誘う。
[Art / 音楽]
MIT マサチューセッツ工科大学 音楽の授業
世界最高峰の「創造する力」の伸ばし方
菅野恵理子 / あさ出版
1980円(税込)
一流の科学技術者を輩出してきた米国の名門マサチューセッツ工科大学(MIT) 。ここでは主たる科学・工学系の授業の他、人文学や芸術科目にも力を入れており、その中でも音楽を選択する学生は4000名中1500名にも上るのだという。 なぜ彼らは科学と並行して音楽を学び、創作し、演奏するのか、そこから一体何を生み出そうとしているのかを、カリキュラムやインタビューを通して探る。 世界最高レベルの学生と教師が繰り広げる授業の内容は、知的でエキサイティングだ。
[Art / 音楽]
憂鬱と官能を教えた学校 上、下
【バークリー・メソッド】によって俯瞰される20世紀商業音楽史
上巻:調律、調性および旋律・和声
下巻:旋律・和声および律動
菊地成孔、大谷能生 / 河出書房新社
上巻1155円、下巻1045円(各税込)
ポピュラー音楽のために生まれた理論体系、バークリー・メソッドの本質とはいったい何か? モードやコード、ポリリズムなど、時々聞くが門外漢には図り難い音楽用語の解説と共に、当時の商業音楽の様々な事情を、軽妙な語り口で概観する。菊地成孔と大谷能生、二人の音楽家の講義録。
[Art / 音楽]
すごいジャズには理由(ワケ)がある
音楽学者とジャズ・ピアニストの対話
岡田暁生、フィリップ・ストレンジ / アルテスパブリッシング
1980円(税込)
ジャズ演奏を聴いていて、何かすごいことをやっている気がするが、何がすごいのかわからないという経験はないだろうか? 伝説の名演が具体的にどのようにすごいのかを、音楽学者とジャズ演奏家との対話の中から探る。簡単には読みづらい部分もあるが、インターネット上に用意された関連動画の助けも借りながら、名演の名演たるゆえんを、少しずつでも解読できた時の感動はひとしお。歴史や社会背景ではなく音楽構造を、初心者にもわかるように解説してくれる本は貴重だ。
[Science / 脳]
新版 音楽好きな脳
人はなぜ音楽に夢中になるのか
ダニエル・J・レヴィティン / ヤマハミュージックエンタテイメントホールディングス
2090円(税込)
私たちの脳は、どのように音楽を受けとめているのか、ミュージシャン、音楽プロデューサーを経て、音楽認知神経科学者に転身した著者が語る脳と音楽の関係。音色やリズム、ハーモニーを聞き分ける時の脳の反応、専門家と愛好家を分かつものは何か、なぜ私たちはある種の音楽に惹かれるのかなど、興味深いトピックに惹かれて読み進んでいくと、複雑に連携しながら音楽情報を処理する脳そのものが、その時聞いている音楽に共鳴しながら、美しく精妙なアンサンブルを奏でているようにも思えてくる。
[Art / 音楽]
新装版 世界の調律
サウンドスケープとはなにか
R. マリー・シェーファー / 平凡社
2530円(税込)
「サウンドスケープ」とは「耳でとらえた風景」である。それは音楽の形成や騒音の発生を、両者の間の無数の音と共にとらえることを可能にする枠組みそのものである。神話時代から現代に至るサウンドスケープの歴史から、「サウンドスケープ・デザイン」という新たな音楽活動のための分析や実践の問題までを射程に収め、創造的な「音の思想」として集大成した作曲家シェーファーの代表作。文庫化。
[Art / 音楽]
デレク・ベイリー / 工作舎
2530円(税込)
フリー・インプロヴィゼーションを牽引したギタリスト、デレク・ベイリー。彼が世界各地の伝統音楽や現代音楽、ジャズ、ロックなど、様々なジャンルの即興演奏家たちと対話し、自らのフリー・インプロヴィゼーションについても語る。フリー・インプロヴィゼーションと一般的な即興との違いは何か、どこまでも求道的に突き詰めていく姿勢は、独特の緊張感と充実感に満ちた、彼の音楽そのもののようにも感じられる。
[Art / 音楽]
堀米ゆず子、鈴木学 他 / 春秋社
2970円(税込)
グルーヴとは何か? ノリ? 体を揺らしたくなるような心地よさ? 改めて聞かれると、考えこんでしまうこの言葉について、民族音楽学者が、様々な楽器の演奏家に話を聞きながら、西洋クラシック音楽に於けるグルーヴというテーマを掘り下げる。 演奏家たちの言葉は、それぞれに多様で個性に溢れていながら、一つの共通点を内包しているようにも思われ、グルーヴという名状しがたい何かが、確かにそこに存在しているのだということを感じさせる。