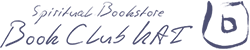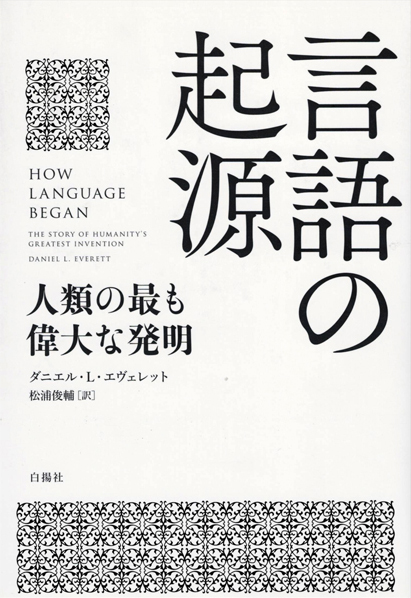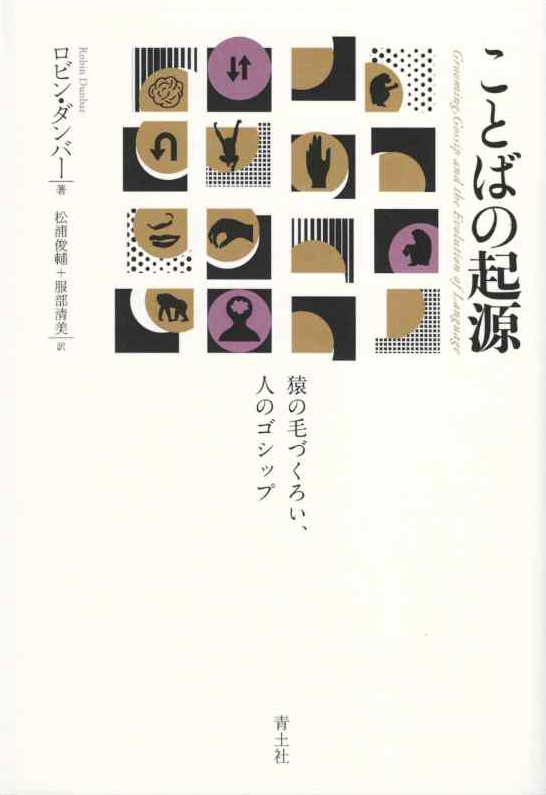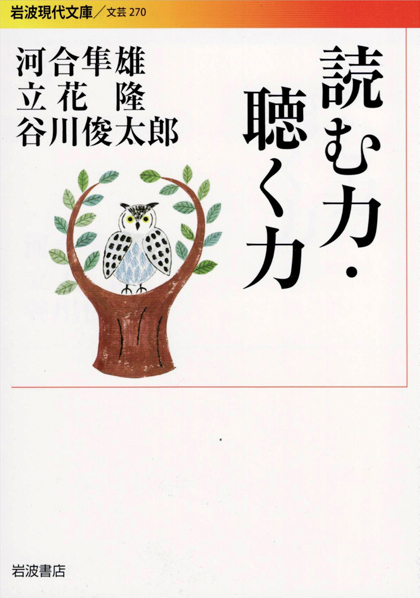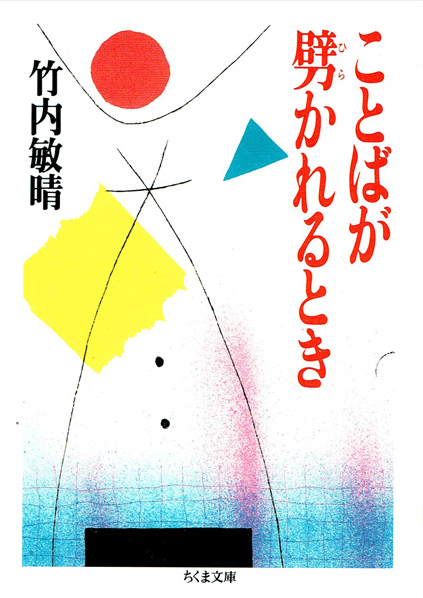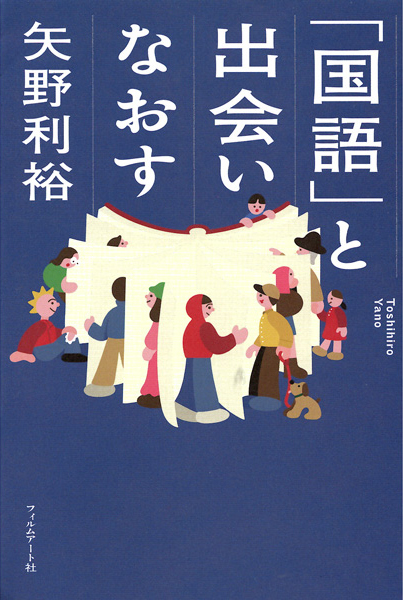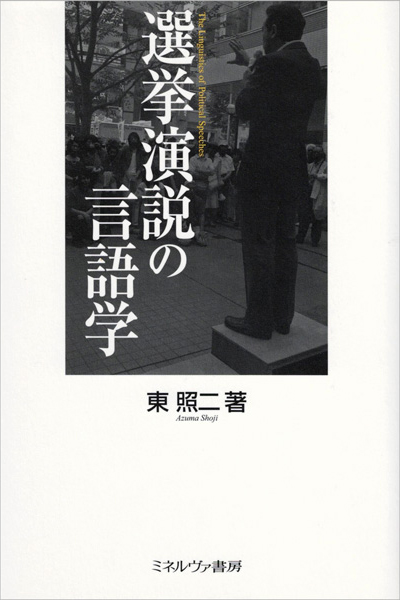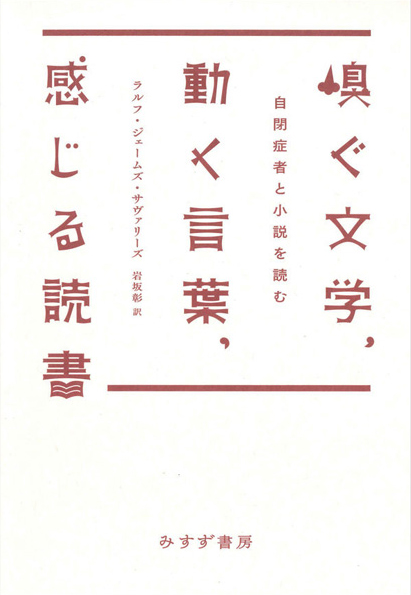2025年10月 満月のたより
言葉の魔力、魔法の唱え方
言葉が無くても、気持ちが伝わることはあるし、必要なことを行っていけば、社会は動いていくかもしれない。しかし、人は自分の意志とは関係なく言葉を与えられ、憶えることになった。言葉を手にした人間は、他者を扇動したり、争ったり、また不用意に傷つけることもあれば、自身の心の動きや社会の動向を定義したり、探り疑うこともある。また同時に、他者に知恵を授け、想いを伝え、癒し、それが新たな他者との付き合いなど、何かのきっかけになることもあって、言葉はそんなことも不思議と可能にしてくれる。
私たちは普段、言葉を話しているのに、言葉そのものについて意識することは多くないだろう。言葉というものが世界になぜ現れたのか、そしてどうしてそれを人類が使うことになったのか、それらを人間自身が説明をすること、つきつめて考えることはとても難しいからだ。
こんなふうに、言葉をどこか魔法めいたものと考えるなら、言葉のメカニズムに自覚的になることで、その魔力を使えるようになるのかもしれない。
エジソンは独力で電球を発明したわけではない――その一〇〇年前にフランクリンが電気の分野で行なった成果が必要だった。一人で成し遂げられる発明は存在しない。誰もが文化の一部であり、誰かの創造性、アイデア、先行する試み、自分が住まう知識の世界の一部をなしているのだ。あらゆる発明は時間をかけて、すこしずつ積み重ねられていく。言語もまた、例外ではない。
[Society / 言語・文字・記号]
ダニエル・L・エヴェレット / 白揚社
3850円(税込)
なぜ言語というものが生まれたのか? コミュニケーションには言語が必要なのか? 言語とは一体何なのか? 本書は、アマゾン奥地に暮らすピダハン族の言語研究で知られる言語学者が、言語学、人類学、考古学、脳科学などの多面的なアプローチで、人類が発明した言語の進化史について刺激的な考察を展開。文化と言語の関係を紐解きながら生成変化していく言語のありようを探求する。
[Society / 言語・文字・記号]
ことばの起源
猿の毛づくろい、人のゴシップ 新版
ロビン・ダンバー / 青土社
3080円(税込)
言語によるコミュニケーションにおいて、時に事実を羅列するよりも、物語性のある方が信憑性を感じやすいことがあるのはなぜか。本書は、進化生物学の観点から、サルの「毛づくろい」に代わる情報伝達手段として噂やゴシップが言語へと進化した、という大胆な仮説を提唱している。
[Life / 思考法]
河合隼雄、立花隆、谷川俊太郎 / 岩波書店
924円(税込)
著名な有識者3人のセミナーを収録した本書を読むと、人の等身大の日常に寄り添った柔らかい言葉で話が進んでいる、という印象を受けるはず。「読む」、「聴く」。その一見受動的なことが、実は能動的なことであるというのは、本書に触れることで腑に落ちるだろう。しかしながら情報過多社会でその能動性はむしろ作為的に利用されるものにすらなっているのかもしれない。スマホやパソコンの登場を経て、いつでも人の主張や思惑を聞いたり考えたりすることの増えた現代において、本書は、あらためて人間の生活に根差した次元にある「読む」「聴く」に自身を立ち返らせてくれる。
[Body / ことば・声]
竹内敏晴 / 筑摩書房
748円(税込)
幼い時に耳を患い、12歳から16歳の間は耳が全く聞こえず、喋ることもできずに外界とのコミュニケーションを断たれていた著者は、必死に言葉を回復しようと試みる過程で言葉と体のつながりを深く追求することとなる。私たちが普段発している言葉は、他人に対して本当に届いているのか? 世界に対して開いているのだろうか? 一度、感覚的に自分の発した言葉をモノとして捉えてみるとよくわかる。ボールを相手の胸に投げるように、言葉を発しているか、それともどこか遠くの方に投げているか、自分の目の前に落っことしてはないか。コミュニケーションの原点がたぶんここにあるのだろう。世界を拒否している人の体はこわばっている。声も通らない。体が開き、心も開いている時、初めてまっすぐな言葉が投げられるのかもしれない。体、健康についてはこの著者以外にも、地道な研究を行った本が数多くあり、それぞれ価値があり、すばらしい。それは知識による研究ではなく、本当に身を持って学んだことから出てくる言葉だけが持っている輝きなのだろう。
[Society / 教育]
矢野利裕 / フィルムアート社
2530円(税込)
言語に収まりきらないものを表現する文学は、芸術と呼ぶにふさわしい。では、テストや教育の中の「国語」は、果たして文学の本質に触れているのだろうか。国語と文学が心に与える揺らぎ方に大きな違いがあるのは、なぜだろうか。国語教師は必ずしも文学青年とは限らず、逆に作家や物書きの多くは、国語教育に関心がないという。現役の国語教師であり批評家でもある著者が語る、新たな国語・文学論。
[Society / 政治・経済]
東照二 / ミネルヴァ書房
3465円(税込)
人々を惹きつける演説にはどんな特徴があるのか? 社会言語学者がフィールドワークで集めた2009年8月の衆議院総選挙前における演説を事例に、日本の政治家とロナルド・レーガンやバラク・オバマといった海外の政治家の演説を比較分析する。「謙譲語が多いのはなぜか」「カリスマ性はどのように生まれるのか」といった素朴な疑問を解き明かしながら、政治の本質に迫る。演説時の言葉遣いを中心に政治家の思想や性格を読み取ろうとする本書は、読者が政治家を目指すかどうかにかかわらず、言葉で人に考えを伝えようとする際のラポール形成、コミュニケーションや表現の土壌を育んでくれるだろう。
※古書のため価格を変更することがあります。
※傷、シミ、折れなどがある場合があります。
※返品交換不可とさせていただいております。予めご了承ください。
[Mind / 発達障害]
嗅ぐ文学、動く言葉、感じる読書
自閉症者と小説を読む
ラルフ・ジェームズ・サヴァリーズ / みすず書房
4180円(税込)
6人の自閉症者と文学教授が、『白鯨』『アンドロイドは電気羊の夢を見るか?』『心は孤独な狩人』などの名作をともに読んだ読書セッションの記録。理論など持たず、また想像的な遊びもできないだろうという外部からの思い込みを覆し、感覚を通じ、物語と独自の仕方で関わる自閉症者による、鮮やかで豊かな読書体験が浮かび上がる。