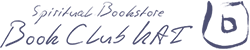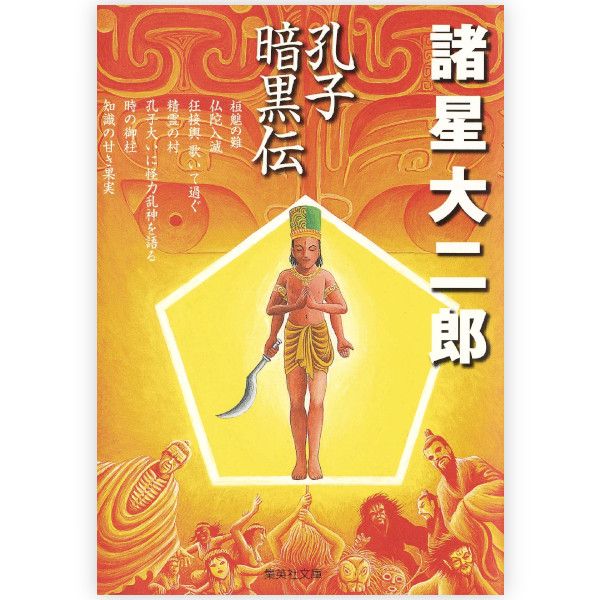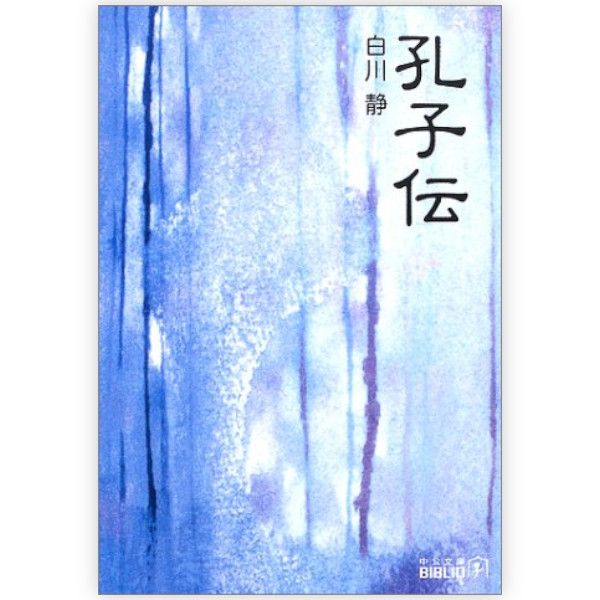interview archiveは、過去のNewsLetter、spiritual databookで
インタビューをした方々の記事です。
内容や役職なども当時のものです。
掲載の内容も、インタビュー当時のものを
そのまま掲載しております。
予めご了承下さい。
SPECIAL INTERVIEW ARCHIVE #01
酒見賢一氏に聞く
作家
今回のニューズレター(※1991年春)では、そのユニークな創作活動で、注目を集めている、作家、酒見賢一氏に、お話を伺うことにしました。酒見氏の作品には、いつも、魅力あふれる光道者が登場します。知的興奮を誘う新しい才能は、どこから来たのか、また、本とどの様につきあっているのかをお聞きしてみました。
B―酒見さんの作品は、デビュー作『後宮小説や、現在連載中の「陋巷にあり」など、奇想天外な物語を、古代中国を舞台に展開されていますね。どこまでが史実なのか素人には判別できませんが、膨大な知識をもとに独創的な解釈が行われている様で、これは、新人作家としてはたいへん異色の存在だと思うのですが….。
いやあ。なんか、中国のについてものすごく詳しい作家だと思われていて、まったく困ったもんです。
たしかに、大学では中国を専攻しましたけれども、それ程おもしろい勉強をしていたわけではないんです。
大学で専攻したのは、東洋哲学科というんですが、本当ならインドをやりたいと思って入ったんですよ。ウパニシャッドとか、原始仏教とか。ところが入ってみたら、うちの学校には中国をやる先生しかいなかった。また中国をやるにしても、どうせなら老子や荘子なんかの道教思想の方がおもしろそうですよね。
だけど、うちの先生はやってないんですよ。何をするかって言うと、思想的な研究などほとんどやらないで、ただひたすら漢文を読む。学問なんていうのは、皆そういうものだと思うんですけど、昔の事を知るための手段は非常に限られています。
中国のああいう思想とか歴史が文献として残され始めたのは、漢代からですから、春秋時代を研究するということはあのへんの文献を読むしかないんです。
それで、一年間で懸命にやって20ページぐらい読むというペースですから、ちっとも進みません。とてもじゃないけれど哲学を語るところまでいかないというわけです。
だから今も、必死になって調べながら書いているんですよ。知らんことを書くんですから大変です。孔子をライフワークにして、一生やってらっしゃる先生もいるのに、僕なんかがいきなりいいかげんな事をやっているわけですから、恥ずかしいです。
B―そうだったんですか。ということは、もともとは中国に限らず、いろいろな哲学や宗教に興味をお持ちだったんですね。酒見さんの精神世界における歴といいますか、特に、どんな本に出会い影響を受けられたのかお聞きしたいのですが、そもそも、いつごろからこういう世界にひかれだしたのですか?
それはもう子供の時から好きでした。SF小説やマンガばかり読んでましたけどね。そういう子供は好きでしょう、神秘的な事が。僕らの世代だとマンガを読んでいない人はいないですよね。当然僕も影響を受けていると思います。
『デビルマン』なんて今読んでも涙が出ます。神とか悪魔とか。考えちゃいますよ。諸星大二郎の『孔子暗黒伝」もおもしろくて、これは今書いてる連載にまでつながってきてるんじゃないかな。SFではアシモフとかハインラインとかそういうものをよく読みました。そのあと高校生の時だったかな、平井和正の『幻魔大戦』が始まって、おもしろいと思いましたよね。『幻魔大戦』のテーマは、結局“求道と自覚ですものね。
B―なるほど。最初はフィクションだったんですね。
そうです。だいたい小説家になるぐらいですからね。そういうものが好きなわけです。
具体的な精神世界としては、その頃、ヨガに興味を持ち出して、沖正弘さんを読みました。沖ヨガの哲学は、全面肯定ということでしょうか。すべてを正しいと言うことにするんです。
夏、暑かったら暑いのが正しいと言うんです。寒かったら寒いのが正しいと。それにつきます。病気をしたら病気をするのが正しい。自分が不自然なことをしたから体が知らせてくれてるんだと。
あの当時の人達、桜沢如一とか天風とか鈴木大出とか、凄いですよね。東洋思想を全体的に見ていてヨーロッパやアメリカで評価されてましたし。本当にこの人達は求道者だと思います。
それから気の理論なんていうのはだいぶ調べましたね。インドの気と中国の気は、ちょっと違います。
あと易経は好きです。儒教の経典なんて、堅苦しい物ばかりなんですけど易経は例外ですね。なんでこれが儒教なのか。ニューサイエンスの人なんかもおもしろい。まあ、とにかくこういう世界自体は好きですから、本屋に行けばそのジャンルの場所には必ず行きますよ。
B―何かを知りたいと思った時、どのように本を探されるのですか。
例えば、『後宮小説』の時は、房中術が出てきますが、あれは漢代の書物があるんです。ところがそれは中国ではもう滅びていて、平安時代に伝わったものが日本だけに残っているという。『医心方』という中国医学のあらゆる体系の本です。全百巻。探していたら、なぜか知らんけど、その中のたまたま一巻だけを大学の図書館でみつけたんです。
しかもそれが偶然にも読みたかった房内編だったから、びっくりしましたよ。そういうこともあります。普通は、大学の図書館とか本屋にいくわけですけど、豊橋の本屋ではなかなかこういう種類の本は、置いてくれないです。
どうしても欲しいと思ったら注文します。でも絶版だといわれることも多い。本当は興味を持った本はすぐ買っとくべきです。すぐなくなっちゃいますから。ただこういう本はおおむね高いですから、なかなか買えないんですよ。
それで後で後悔する。またタイトルがかっこいいんです、この手の本は。今の『G巷にあり』に関しては、白川静先生の『孔子伝』というのが非常におもしろかったです。加地伸行さんの『孔子」も。
B―孔子やその弟子の顔回については、調べ尽くされている筈なのに、それでもまだわからないというのが不思議ですよね。
倫理思想として長い間使われていますからね。そのための学問になってしまったし。本当は、2500年前の空気というのがありますよね。これをまず自分で理解できないとどうしようもないと思います。
今の学会の評価だと、孔子というのは、合理的で、神秘的なことは否定して、いわゆる教育者であったと言われていますけど、文化人類学的に調べていくとどうもそうではないんですね。
当時は今で言う迷信みたいなのが常識として通用していた筈なんです。おまじないとか、お化けとか。孔子だけ例外ということは有り得ない筈です。思想というのは発達していくうちにどんどん複雑になっていく。けれどももともとはピュアですよね。キリスト教なんかでも、モーゼやイエスが言った頃は、だいぶ単純であったと思うんです。原始仏教に興味を持ったのも、今の仏教とずいぶんちがうんだなあと気がついてからです。
それで、パーリ語原典を訳したものとか、釈迦の生涯を記した本を読んだりしました。このへんの言葉を読んでいると、釈迦の教えは、もともとはそんなに複雑なものではなかった。神秘的なことも殆ど出てこないんですよね。キリストと違って、不思議なことをあまりやらなかった。時々、しかたなくっていう感じでやったりしましたけど。そういうピュアで複雑じゃないところがいいなあと思います。
B―本を書こうとするとき、そのテーマやキャラクターは、どのようにして決定されるんですか。
僕はテーマなんて意識してないです。ただ、思いついただけです。
だから、問い詰めていくとインスピレーション、思いついたとしか言えないと思います。作家というのは神秘的な職業だと思っていますけどね。詩人にしても作家にしても言霊使いというわけでね。言葉というのがいかに凄いかっていうのは、例えばある小説を読んで人生が変わったっていう。
これは、凄いことです。人の人生を変える力が小説にあったということですよ。小説家は気をつけなくてはいけない。僕の小説なんかみんな嘘ですから信じないでください。
B―精神世界の本についてはどうお考えですか?
こういう精神世界に多くの人が興味を持ち始めているということ、これは世界的な傾向ですよね。これは考えなくちゃならない。ただ、僕は一歩まちがえると非常にこわい世界だと思うんですよ。唯物主義はどうしても気に入らないんけれど、だからといって現実の問題を他の次元に求めるのは、どうもよくない気がする。だいたい精神世界を本に書けるのかどうかということ自体僕はわからないし、もう一つは、煽るような本が非常に多いわけです、このジャンルは。
孔子は神秘的な世界に対して、「敬して遠ざけよ」と言っています。これはそういうものを否定しているのではなく、「信じているから敬うけれども遠くへ置いておく方がよい。」という意味です。生半可な気持ちで手にとってはいけないのだと。修行とは、自然に生きるということで、得体の知れないものをもてあそぶことではないということだと。
また、沖ヨガでは、解脱というのは、100%神経が目覚めた状態をさします。それは、正しいことを正しいと感じられる。いい物を見たらいいと感じられる。
つまり神秘的なものと現実を区別しないで生きるということです。とは言っても僕自身、悟りをひらくことに憧れますよね。そういう本も好きですし。好きなんだけれどこわい。いろいろありますからね。だから、読んでみて、これは少し変だと思ったらやめる。自分にとってよくないものには違和感を感じるはずです。
それから、実際にやってみることも大切だと思いますよ。情報だけ聞きかじっていても意味は無いですから、できることはやってみて、よくなければやめる。知行合一。知ることと行うこととは同じでなければならないということですよね。
もっとも作家というのは、どうしても頭に偏りがちですから矛盾を抱えてますけど。でも僕は変わっていくことが正しいと思っています。だから、一年後は、ぜんぜん違うことを言ってるかもしれない。わからないことばかりですよ。わからないから書くんです。
B―酒見さんの作品には、そういうピュアなものをかたくななまでにひたすら求めていく沈道者が多いですね。ピュタゴラスやエピクテトスもそうだと思うんですが。
そうですね。ある方向性を決めてやっている訳ではないんですが。ただ、なんとなく気になったことを書きたくなるんです。ピュタゴラスなんかも中学の数学で定理とか出てきますけど、ちょっと調べてみると非常に宗教的な人だったというのがわかるわけです。
彼は音楽を特別のものとして重要視したりしている。なぜか孔子もそうなんですけどね。まあ、そういうピュアなものを求めていった人というのは、必ず反体制となってしまいます。反体制思想家だったからこそ、孔子も国を追い出されて放浪せざるをえなかった。やっぱり特殊な思想を持って、嫌がられたんでしょうね。釈迦も当時のバラモン教に楯突きましたよね。そういう意味ではニーチェやキルケゴールなんかもおもしろいから、いつか書きたいと思います。キリスト教に楯突いたから。フロイトもそうかもしれない。
B―現在、小説新潮に連載中の『きにあり』は、偶然にも回”という名の孔子の弟子が主人公となっているので毎回楽しみに読ませていただいているのですが、いつごろ完了予定になりますか?
目安としては、前編800枚、後編800枚だから、1600枚ぐらいです。でもわからない。最低でも3年はかかると思います。顔回については、あまりよくわかっていないんですけれども、弟子なのに名が残っていること自体、非常に珍しいことだと思います。
実在の人物の歴史にのっとって書くから、ストーリー構成というのは自ずからできるわけだけど、その時、何を喋らせ、何を感じさせるのかなんていうのは全然わからない。まあ、その時になれば、また思いつくでしょう。
B―それは、ますます楽しみですね。今日は、本当に、どうもありがとうございました。
1991.spring
酒見賢一 sakami kenichi
1963年福岡県久留米市生まれ。愛知大学文学部卒業。
専攻は中国哲学。1989年第一回日本ファンタジーノベル大賞受賞。愛知県豊橋市在住。
著作に「陋巷に在り」、「後宮小説」、「ピュタゴラスの旅」他
※役職などはインタビュー当時のものです。

Related Books
【used】陋巷に在り1
酒見賢一
新潮社
440円(税込)
論語で伝えられる逸話や人物を操りつつ、大胆な発想で孔子の生涯を描いた歴史長編。孔子の愛弟子・顔回が生きるスピリチュアル物語。シリーズ全13巻。
●古書のため現在の在庫が切れると価格が変更することがございます。
値が上がる場合のみ、こちらからご連絡いたします。
●なるべく状態のよいものを選んでおりますが、傷、シミ、折れなどある場合がありますのでご了承ください。
●お買い上げ頂いた古書の返品、交換は受け付けておりません。
何卒ご理解の程よろしくお願いいたします。
●シリーズ全13巻をご希望の方は、お手数ですがメール、電話などでお問い合わせください。
お問い合わせページはこちら
孔子暗黒伝
諸星大二郎
集英社
792円 (税込)
その独特の作風と発想で、異彩を放つ漫画家諸星大二郎による、もう一つの孔子伝。時空を駆け巡り老子や釈迦も登場するSFロマン。
孔子伝
白川静
中央公論新社
984円 (税込)
漢字研究の世界的第一人者である著者が描いた孔子像は、これまでの先入観を打ち砕くインパクトを持っている。孔子が起こした儒教と言えば、親を敬い、礼をつくすという、現代の道徳の基礎を作った思想のはずであった。しかし孔子の出生は、そのようなイメージとはまるでそぐわない、呪術集団を母体としていたことが本書で明らかにされている。孔子は、表面的には道徳を説く思想家であったが、その実体は、欲望うずまく当時の中国の中でもかなり特殊な立場にある神秘家であったというのだ。広く世に知られている孔子の言葉の数々も、そうした観点から眺めてみると、これまでとは違った意味を感じさせてくれるから不思議だ。中国には孔子以外にも思想的な巨人がたくさんいる。道を説いた老子、性悪説をとなえた旬子、独特の平和思想を提唱した墨子など、それぞれの独自の思想は、現代まで影響を及ぼし続ける力を持っている。なぜ中国にはこのように思想的な巨人達が数多く存在したのか。それは、もしかしたら漢字とメディアの存在が、そもそも呪文的な質を備えていたことが関係しているのかもしれない。文庫。