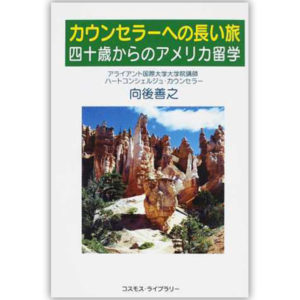Special Interview #23
不安なら、話そう。
カウンセラー / 向後善之

コロナウイルスの打撃で社会の閉塞感が高まり、孤立感が深まりました。
今、あらためて「人と向き合う」ことの大切さを痛感している人も多いのではないでしょうか。
ここ最近、私たちは、自分ではない誰かと話すとはどういうことか、わからなくなっているのかもしれません。
生きていくことの根本にあり、誰にでも関係がある、このあまりにも基本的ながら、
実は難しい行為をめぐって、臨床心理士の向後善之さんにお話をうかがいました。
不安感が強くなっている
向後善之さんは臨床心理士。うつ状態や心の病、ひきこもり、不登校、職場での人間関係やパワハラなど、人々が抱えている悩みに耳を傾け、相談者を支援するカウンセラーだ。
その向後さんは、ここ数年、世の中の不安傾向が一段と高まっているのではないかと懸念する。
「だいぶ前からありましたけど、ここ数年くらい、グッと顕著になってきたような気がします。いま、先の見えないことが多いですよね。支払い続けても将来ちゃんと年金がもらえるかどうかわからないし、終身雇用制なんてとっくに崩壊している。やたらに罵倒するなど攻撃的な人が多いのも特徴で、攻撃って不安の裏返しなんですね。ハラスメントもそう」
確かにSNSなどでも、ちょっとしたことですぐ「炎上」してしまう傾向が昨今は強い。
「SNSは極論同士の激突で、対話がないですね。正論と正論だからどうしようもない。ケンカしなくて済むのは、狭いサークルの中だけの会話で、だからセクショナリズムになります。どんどん細分化されてしまう。会社なんかでも、自分たちの部署さえ良ければいい、という考えが横行してますね。全体を見ようとしない」
こんな話をしながらふと、向後さんは「若い人のほうが案外、まともだったりしますね」と語りだす。
「高校生くらいの子と話していて音楽の話になり、最近聞いている曲なんか教えてもらうんです。もちろん、ぜんぜん知りません(笑)。で、YouTubeで探して聴いてみるとなかなか良くて、歌詞もね、それこそジョン・レノンじゃないけど社会性があったりする。あんまりマジメ過ぎてもイヤだけど、こういうのを好んで聴くんだなって、新鮮でした。今の若い人って、生まれたときから景気が良い状態を一度も経験してないですよね。ですから、言葉の本来の意味で自立しているところがあるのかもしれません」
向後さんは1957年生まれの64歳。ジョン・レノンの名前が出たが、ビートルズに「When I’m Sixty Four」という曲がある。これは夫(と思われる男性)が妻(もしくは家族)に「64歳になってもぼくを必要としてくれるかい?」と歌う内容だ。そしてそう、幸か不幸か、今のような閉塞状況でこそ、先に引いた高校生に希望を見出すような、そんな心のやわらかい、開かれた64歳のカウンセラーが必要なのである。
ちなみに蛇足だが、「When I’m Sixty Four」は「社会派」と言われたジョン・レノンではなく、ポール・マッカートニーが16歳の時に作った曲で、1966年、ポールの父親が64歳の時にレコーディングされている。そしてポール自身はなんと、64歳の時に奥さんと離婚して……。いやいや、もうこれくらいにしよう。
40歳でアメリカ留学
話を64歳から24年前に巻き戻そう。40歳の時、向後さんは勤めていた石油会社を辞め、アメリカに留学した。
「自分は少しヘンなんじゃないか、という感覚はずっとあったんです。どうも周りの人と合わないし、すぐ顔が赤くなっちゃうし。で、高校2年の時に東京の渋谷に大盛堂書店ってありましたよね。あそこでなんとなく宮城音弥の『精神分析入門』という本を手に取ったんですね。それが面白かったのと、プロフィールを見たら、東京工業大学教授とある。へええ、と思いました。私は理系の人間で、心理学とか精神分析、心の問題ですよね、そういうのはすごく遠い存在だと思っていたんです。でもこの人は東工大で教えているわけで、そのあたりから気にし始め、石油会社時代も心理学の本を読み続け、カウンセラーという職業に興味を持つようになりました」
とはいえ、すぐにアクションを起こしたわけではない。年齢が年齢だし、石油会社は15年続いていたし、そう簡単に現在の環境を捨てる勇気もない。
「それでもいろいろ調べて、ポツポツ、ワークショップに参加するようになりました。自己啓発系の合わないヤツなんかもありましたけど、ある時、参加者全員の前で一人ひとり、“自分は何者か”について表現する、ってのがあったんです。ぼくはこれが全然できなくて、ずっと居残りで、とうとう夜中になってしまって……。そしていよいよ追い詰められてまわりを見たら、参加者が皆、ぼくを見ている。その時、「ぼくは皆と仲間なんだ」と感じ、そのことを話したら、歓声があがって、OKをもらいました。そしたらね、この経験のあと、長年ずっと悩んでいた頭痛と肩こりが嘘みたいにピタッと治ったんです」
向後さんはなんと、小学生の時からずっと頭痛薬が手放せなくて、ご自身の言葉で言うなら「頭痛薬ジャンキー」だったという。それがあっさり消えてしまったのだ。そして奥様が離職と留学に理解を示してくれたこともあり、とうとう一歩を踏み出すことになる。このあたりの逡巡、そしてアメリカでの貴重な経験は、ご著書『カウンセラーへの長い旅四十歳からのアメリカ留学』(コスモス・ライブラリー)に詳しいので、ぜひご一読いただきたい。
「日本では、組織の中にいると、そもそも上司はじめ上のほうの人と意見が違ってしまったらもうアウト、という空気があるじゃないですか。アメリカはそれが全然ないんですね。何かぼくがヘンなことやってしまうと、日本なら“何やってんだ、お前!”となるけど、アメリカ人は違う。“なぜそんなことするのか?”って興味が先に立つ。どういう考えでそんなことするのか検討してみようじゃないか、という雰囲気になるんです。そうなると話を聞いてくれる。そして、“私の考えと基本的には違うけど、一理あるね”と認めてくれます。4年半アメリカにいたけど、一度も怒られたことないですね。これ、日本とは決定的に違います。アメリカはいろいろな文化的ルーツを持つ人が集まってる国だから、そういう背景が大きいのかもしれませんね」

自分は少しヘンなんじゃないか、という感覚は ずっとあったんです。
靴泥棒の話
そしてまた時空を遡ろう。グッと加速して小学生の頃。そう、「頭痛薬ジャンキー」の時代だ。
「周囲と合わない、という話をしましたが、30人とか40人くらいの人数の前で何かを話すのがほんとうにダメで、必ず赤面してしまうんです。1対1とか少人数は平気だし、逆に500人以上など大人数も平気。中間だけがダメ。これ、日本にいる時にはまったく理由がわかりませんでした。でも、アメリカに留学してそのくらいの人数で授業を受けている時に気付きました。ぼくは実は小学生の時にある決定的な経験をしていて、それがずっと尾を引いていたのです」
向後さんは小学2年生の時、まったく身に覚えのない靴泥棒にされてしまう。
「クラスメートの靴が盗まれ、ホームルームで問題になったんです。でも誰も名乗り出ない。そしたらある女の子が、“私、昨日○○くんと向後くんがケンカしてるのを見ました”と言い出して。それでみんなの視線がこっちに集まって、先生も“許してやるからさっさと認めろ”みたいになってきて。ぼくはやってないんですけど、その時ガーッと押される感じで、ああもうこれはダメだと思い、“やりました” と言ってしまいました。
でもそこで終わらなくて、“盗んだ靴はどこへやったんだ?” と先生が聞くんです。これは想定外(笑)。しかしそこは2年生でも機転が利いたんですね、『焼却炉で焼きました』と、とっさに答えました(笑)」
ここまでを鮮明に憶えている向後さんは、その先の記憶に関しては真っ白だという。後日、どうやらあいつが真犯人ではないか、という見当がついたものの、向後さんは名誉挽回に出ることはしない。そうだ。やってもいない犯罪をやったと言ってしまう心の持ち主は、後日逆襲に出るようなことはけっしてしない。良いことを言ったと思っている女子も教師も、(こんな言い方はマズいかもしれないが)ある意味、特に悪意があるわけでもないごく平凡な人たちなのだろう。
「それがね、アメリカにいる時に出てきたんです。わかったんです、アレだって。あの時だって。ぼくが30人から40人くらいの前で話す時赤面するのは、ちょうど1クラスぶんくらいの人数だからなんだ、って」
「オープンダイアローグ」と「リフレクティング」
もう1冊、本を紹介したい。同じく臨床心理士の久保田健司さんとの共著で、『マンガでやさしくわかるオープンダイアローグ』(日本能率協会マネジメントセンター)という本がある。表題の「オープンダイアローグ」とは、相談者(クライアントと呼ばれる)に対して臨床心理士1人が対するのではなく、医師や看護師、ソーシャルワーカーなど各分野の専門家が集まり、同時に係わることを意味する。そして本書でもう一つ重要なのが「リフレクティング」と呼ばれる概念。これは、クライアントの悩みや症状に対し、集まった専門家たちが議論するにあたって、クライアントを交えず、しかし目の前で話し合うことを指している。クライアントは目の前で複数の専門家が自分についてあれこれ話すのを聞きながら、しかし発言はしない。話してはいけない、ただ聞いてなければいけない、と表現するとなにやら辛そうだが、口を挟まずにじっと耳を傾けることで自分の状態を俯瞰的に捉えることができ、たいへんに効果的だという。
「ダイアローグ(対話)は立場や意見の違う人同士が話すことに意味があるので、そこには仲間同士の会話みたいな心地よさや都合のよさはありません。でも、思いもよらない気づきを得られることがある。少し考えればわかることですが、とことんバラバラな存在がただ集合しているわけではなく、今の状態を変えたい、そのためにどんな方法がいいか一緒に探求していきましょうという合意が、クライアントと専門家たちに共有されているわけです」
臨床心理士である向後さんの元には、さまざまな悩みを抱えたクライアントがやってくる。たとえばDV。どうしても殴ってしまう、加害者になってしまう自分をなんとかしたい人たち。
「あんただって奥さんを殴りたいと思うこと、あるだろう? 殴ったことは? なんて挑発的に言ってきたりします。そういう場合には呼吸のペースをゆっくり保ちながら話を聴くのです。挑発には乗りませんが、そうしてやり取りしているうちに泣き出したりする人がいて、それは興奮状態だから慎重にやらないといけないんだけど、対話できる下地が少しはできたことにもなりますね。ただ怒りまくって、“金が欲しいんだろ!”と言ってお札をたたきつけて出ていくような人もいますから。ちなみにね、人がキレる時って、指がいつもと違う感じで曲がっていたり、妙に肩が前にせり出してくるようになったりします。こうなったら危ない。逃げる用意をしたほうがいいです(笑)」
靴泥棒の話のように、仲間内だけで盛り上がり、価値観の違う人をひたすら罵倒する人々は、本当に満足しているのか?
もしかしたら私たちは、なんとなく自分の脳の中で勝手に作り上げたイメージだけで他人を判断し、そのイメージとだらだら「会話」しているだけではないのか。そこには自分の知らない他人の姿は映りようがないし、「対話」が生まれるきっかけすらない。
変えたいなら、話してみよう。話したいなら、聞く耳を持とう。コロナで少なからず誰もが閉じ込められている今こそ、話したことのない、でもちょっと気になるあの人や、なんとなく気まずくなって音信不通になったままのあの人、外国からやってきたあの人と対話するチャンスかもしれない。

向後善之(こうご・よしゆき)
1957年神奈川県生まれ。エンジニアとして石油会社に15年ほど勤務したのちに渡米。カリフォルニア統合学研究所(CIIS)でカウンセリング心理学を専攻する。帰国後は帝京平成大学臨床心理学科講師を経て、アライアント国際大学カリフォルニア臨床心理大学院東京サテライトキャンパス講師のほか、ハートコンシェルジュ株式会社でカウンセリングを行っている。著書に、文中で触れた2冊のほか、『人間関係のレッスン』(講談社現代新書)などがある。
Related Books
カウンセラーへの長い旅
四十歳からのアメリカ留学
向後善之
コスモス・ライブラリー
1760円(税込)
1つの道を生涯追求する選択もあれば、それまで続けてきた仕事とは全く別の道に足を踏み入れる選択もある。本書は、向後善之氏が、あるアメリカ人セラピストに出会ったことがきっかけで、四十歳の時に留学を決意。長年馴れ親しんだ会社を去り、アメリカへと旅立つ。カウンセリングの実際はもちろんのこと、新しい人生を創造し始めた人の悲喜こもごもが、明るい文体で語られる。
マンガでやさしくわかるオープンダイアローグ
日本能率協会マネジメントセンター
向後善之、久保田健司
1760円(税込)
フィンランドで生まれた「オープンダイアローグ」とは、開かれた対話による、心理療法の治療だ。入院や薬物投与はできる限り行わないかたちで、病や障害を抱えている本人、カウンセラー、医師だけではなく、家族を含めたすべての関係者をまじえて、ただひたすらに「対話」をする。一見、遠回りに思えるこのセラピーが、うつ病や統合失調症、引きこもりなどの治療に大きな成果をあげるという。
わかるカウンセリング
自己心理学をベースとした統合的カウンセリング
向後善之
コスモス・ライブラリー
1980円(税込)
カウンセラーの仕事とは、だれもが持つ、精神的な自己治癒力と自己実現に向かう成長能力を、クライアント自らが再発見していくプロセスをサポートすることにある。本書は、自己心理学をベースとした総合カウンセリング初心者や、最新臨床心理学を学びたい人向けの格好のテキスト。