『Interview Archive』は、『NewsLetter』『Spiritual Databook』に掲載されたインタビューです。
内容や役職などはインタビュー当時のものです。予めご理解のうえお楽しみください。
Special Interview Archive #10 2004
EDGE - 高く、そして鋭く
藤原新也 / 写真家、作家、旅人
自分がいつも生きていたい、ナマモノでいたいという感じ。いつもまな板の上に転がっている魚みたいに、自分を喰いたい。
人間は自分を喰いつつ生きていると思うから、自分を喰うのなら、一番新鮮な自分を喰いたい。
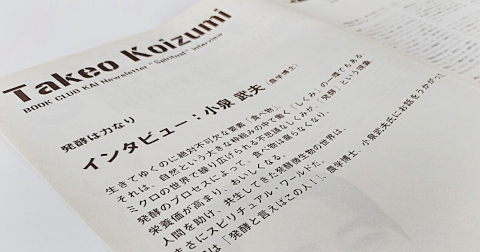
誰の前にも、エッジはある。
このまま同じように続いていくはずの世界と、何が起こるかわからない不穏な世界。
切り立った尾根の先端を、私たちはいつも歩いている。
エッジの位置をどこまで高められるか。
そのことによって、人間や社会のポテンシャルが試されている。
今回は、常に<エッジ>を視野にとらえ続ける、藤原新也氏にお話を伺った。
B (ブッククラブ回) ─ 多くの人が、明日もこの世界は同じように続くと信じ、予定調和の中に生きようとする中で、藤原さんは、逆に予定調和を壊すような、その刹那に体も心も自分の存在すらも賭け、その結果を受け取るような生き方をされてきたように思えます。それはなぜだと自分ではお考えですか?
居心地がよくなると、落ち着かなくなる困った性分なんですよ。自分と予定調和しすぎて生命曲線が平らになってくると、退屈になってくるから、荒れたものにしたいと(笑)。それはやっぱり、生きているという感覚を求めたいという関数が大きいのかな。もともと僕は東京を24歳で飛び出した。あれは1969年だったけれど、あの時代ですら日本という国は空気がのぺっとして、いくら呼吸しても無酸素呼吸をしているような感じがあった。
自分の未来から、ひたひたと酸素の無い時代が来ている、僕個人はリアルにそういうものを感じていて、自分の命を見たい、触りたい、そういう欲求が強かった。人が飢えて死ぬような所に行けば、自分がしっかり立てるのではないかという非常に漠然とした感覚があって、だからインドに行ったんですね。それは結局、自分がいつも生きていたい、ナマモノでいたいという感じ。いつもまな板の上に転がっている魚みたいに、自分を喰いたい。人間は自分を喰いつつ生きていると思うから、自分を喰うのなら、一番新鮮な自分を喰いたい。ある意味、非常に贅沢だよね。それには常にリスクを犯して結界を壊していかないと。
B ─ 一度、新鮮なおいしさを知ってしまったら…..(笑)。
そう、もう腐った肉は食えないからね。流れている水は腐らないけれど、澱むと腐る、というようなことと同じだと思います。人間の体はほとんどが水なわけでしょ。常に体に新鮮な水を通して行かなくてはならない。
ただ、澱んだ水の方が快適だっていう人も多分いると思う。たとえば会社務めして、ポジションを与えられて、家に帰れば家族がいて、団らんしながらプロ野球を見て、風呂に入って寝るというような、常に澱みの中にある快適さというものもある。皆が僕みたいな生き方をしろみたいなことは当然言えないわけだし、世界中の人が僕みたいになったら、世界は成り立たない。
B ─ 藤原さんの有名な、犬が死体を食べている写真は、本当はあるのに、見えなくなっているものを見せてくれたという爽快感がありました。一見、澱んだ水が快適だと思っている普通の人たちも、実は違うものが他にあるという予感を、どこかで感じているような気がします
それはあるでしょうね。やっぱり澱んだ水の中に住んで、それが快適だと思い始めるっていうのは、相当人間が腐らないと(笑)。そこまで腐るのもたいしたものだけど。こういう時代は、自分と整合性を保つというのが難しい。僕のまわりを見ても自分と似たような人はあまりいなくて、やっぱりどこかで妥協しながら常に問題と向きあって、矛盾を抱えながら生きている人がほとんどです。
そういう矛盾の中でジタバタしている人たちが、僕の言葉と写真を見ると少し楽になるんじゃないかと。奈落という言い方もできるんだけれども、何かリアルな本物に触れた時に、風穴が開いて、逆にまた苦しみを覚え始めるというのは、それもやっぱり良いことだと思うんだよね。苦しんでいない人間は、僕は面白くないと思う。どんな些細なことでも、苦しみを持たない人間は生きていない。癒しではなく、苦しみを与えることが生き方を与えることになる。「まあ、この歳になると、だいたいどういう生き方をしている人も、僕は認めるのね。迷いながら、澱みの中で矛盾を抱えて七転八倒して生きていくというのも生き方なんだよね。澱んだ水の中でそれが快適だっていう仮面を見つけて生きていくというのも生き方だし。
僕が贅沢というのはそういう事で、自分は一番うまい新鮮な水を飲んでいる。そういう生活をするにはリスクがいるけれど、それは澱んだ生活をしている人に支えられている。だから僕は僕なりに、そういう生き物として生まれてきた自分を、常に生きていかなくてはならないという宿命をもっている。僕はそのことによって何かを表現をして、澱みの中にいる人に少し反応を起こす。そういう運命の元に生まれてきて、他の運命の人と支え合いながらどこかで均衡を保っているんじゃないかしらね。
B ─ 藤原さんは、まず世界と人を、次に時代を見てこられて、常に独自の世界や時代のエッジを見る人であったと思います。本当は感情も強い方だと思うのですが、藤原さんの文章にしても、写真にしても、どこか「客観」を感じます
風景というのは、見えた通りではないんだよ。見えたそれとは別のものを秘めている。ある時突然バッと変わる。人間の歴史もそうだし、何か見えた時に、一歩入りこんで様子をみると、全然違うじゃないということはよくあるよね。
生理的なものと感情的なものと理性というものがあるでしょう。僕は理性的な言葉を、生理とか感情にするんです。逆の場合もある。人間の言葉、論理とか理知的な言葉というのはそれなりに咀嚼しないとすんなりと入ってこないですが、人に伝えるには、感情と生理が必要でしょう。だからその両極というのか、理性を感情と生理のオブラートで包んで差し出すというね。まあ僕は、40歳後半くらいからそういうふうにコントロールでき始めたのだけれども、20代、30代の頃は混沌としていた。人に伝える方法として、やはり人間は理性の動物であって、それがまず前提になければ間違うことになる。
ただ、その温かい人間観みたいなものは当然必要なわけ。理性と感情と生理というね。それだから、まあ完璧とは言えないけれども、やっぱり言葉だと思っている。一見パッと読んで、非常に情感、感情、生理、ウィット、感触だとかを見たという人がいたとしても、僕はちゃんと理性というものを隠している。
B ─ 最近は、人の関係性について本に書かれていますね
幹があって、何千万という枝葉があって、その枝葉を一枚語ることが文学だという言葉があるんだよね。根っこを語ることは文学ではない。たとえば、「青い」という言葉があるじゃない。青い小僧は根っこを語りたがる。19、20歳の小僧がわかったように根っこを語るというのはよくあるじゃないですか。だけども、一枚の葉っぱの揺れ具合とか光具合とか、そういうことを語るということによって、ずっと根っこまで続いていると思う。
こういう円があるとしたら、円の端と端は非常に近いです。 端っこの方に行けば行くほど、根っこに近くなるわけです。今、言った関係性というのは枝葉の中にある誰もが感じ取れるそういうことだと思う。自分も10年前より少し熟してきたかなって感じかな。
B ─ 様々な物事を体験して、いろいろな視点が増えてくると、普遍的に正しい答えなどないということがわかってきます。藤原さんもそれはよくご存じだと思うのですが、あえて嫌いなものは嫌いというように断言されます。その結果、生じるであろう矛盾やリスクを引き受けるわけですが、そこで「自分はこの立場を取る」と、思い切る基準はどこにありますか?
それはやっぱり伝えたいからだと思う。 今の時代は人に伝えようとするエネルギーがものすごく低下している時代なんだよね。現在(2004年インタビュー時点)、400万人の引きこもりがいるわけだけど、そういう病状として出た人たちが400万人いるということであって、若者に限らず、かなりの割合の人が引きこもり的感性をもっていると思う。人に伝えるエネルギーを失っている。まあ、小泉総理とかは、その典型だと思っているんだけれども、いつも遠くを見て、他者がなく遠目で自分の中を見つめる。あれも一つの引きこもりだと思うんだよね。日本を象徴する人が引きこもり的感性をもっているということが、今の日本を表している。これは、政治、世界情勢、経済、環境、科学、教育、人間を取り囲む全てのものが、いわゆるアポリア(解決不能)という時代でしょ。
思考というのは、たとえば詰め将棋で、どうやったら詰めていけるだろうかとやっていくことだけれど、今はどの将棋をやっても詰むことができないような。結局、いろいろな網の目がこんがらがって、ちょうどその先端にいる時代だということなのだろうけれど。そういうアポリアの時代は、結局個人個人が自分の中に自閉して、自分の身のまわりの快適なことを持続していくことが一番楽なんです。
今、引きこもり的感性というのは、日本人一億二千万人の中にある通底した意識です。若い人たちが特に時代を象徴した意識だとか行動形態をもっているだけであって、中年、老人がそういう時代から免れているわけではない。人がみな断言しないというのはそういうことであって、自分の身を裸になってさらしたらまずいわけです。言葉だとか言語というのはそういう意識や生き方を表すものです。たとえば「僕的な」なんていう言葉がありますが、「僕は」とは言わないで、「僕的に」なんて言うのは、これはある意味すごい言葉だと思う。古今東西、人間の歴史の中では、一人称、二人称、三人称まであったけれど、21世紀に2.5人称なんて奇妙な人称が生まれた。僕の前で若いヤツが僕的という言葉を吐いたら、ぶん殴りたくなるという気持ちはあるんだけれども、そういう言葉を発明した若者というのはすごいと思う。自分を影武者にしてしまうというね。昔の忍術のように弓を射ろうとすると、パッと複数に分裂して見えてしまい、どれがその人かをわからなくするという技を身につけた時代で、それは自己防衛本能から生まれて来たものです。
これは象徴的な意味ですが、先ほどのアポリアを、生まれた時から「もろ」に抱えてしまった子たちがいる。たとえば環境問題というのは、政治、経済、教育などあらゆる人間の活動が集約したものだけど、環境問題を反映した身体を一番背負っているのは若い人たちです。今の赤ちゃんは70%とかそれ位の割合で、アトピーが出てくるようですが、ダイオキシン度という言葉を使うと、僕より若い人は、絶対にそのダイオキシン度が高い。僕が今、ダイオキシンを喰っても、あと20年か30年位生きればいいわけだけど。そういう時代に生まれて、じゃあどうすればいいのかというと、結局標的としての自分をぼやかしていくしかない。だからおまえはちゃんとした自分の正しい言葉を使え、「僕的」などという言葉を使うなと強制することはしたくない。僕個人は「僕的」でありたくないんです。ちゃんと自分に責任を持つために。まわりがあまりにもボケの世界だから、断言しているつもりはないのですが、僕の言葉がそう見えてしまうわけです。ただ、断言したことに拘泥してしまって引きずられると、またまずい。昨日あることを断言しても、今日は、「そうではなく、こう思う」と言ってもいいと思う。断言しても、それをひっくり返せるだけの柔軟性がないとその断言はただの頑固になってしまう。そこでまた自分を壊すわけで、昨日言った言葉と今日言った言葉が違うというのは、一日の中で自分を壊しているんです。常に新鮮な水を飲みたいというのは、そこにあるんです。むしろ頑固一徹に何十年も同じ事を言っているという人を、僕は信用しない。
B ─ 引きこもりに象徴される現代の若い人たちが社会の中心になっていく時、日本はどのような国になっていくと思いますか?
国が生命体だとすると、もうすでに生命カが落ちているのは確かだね。でも、若い人が引きこもったというのは、こういった環境や社会に反応したということで、そこまで自分を追いつめていったということです。引きこもる人というのは、ある意味、 エネルギーを使っている。だから引きこもりをマイナス要因とは考えないで、彼らが自分の殻から出た時に、社会とどういうふうに渡りあえるのかということに、僕は興味があって、ちょっと希望をもってます。
自分をずらして逃げ回った人たちのほうが、当たり障りのない平均的な日本の国家を作るでしょうね。今の状況は、エネルギーが非常に低下しているけど、400万人引きこもりがいるというのは、ある意味で希望だと思う。
B ─ 日本に限らず、現在あらゆるところで、アメリカ的な世界観への行きづまりが現れているような気がするのですが
アメリカというものも、一口には語れないものです。生まれたての子どもは、なんでもできるという全能感を持っているけれど、アメリカにはそういう感性をもった人が多い。過去という重しがないからです。もちろん理性をもった人々も同じ位いるんだけど、アメリカの民族としての基調は、非常に全能感が強い。月までいく民族だからね。これはヨーロッパの文明までずっと辿っていかないと語れないんだけれど、歴史の中には常に、全能感と、それを押さえつける抑圧の波がある。今、全能感がものすごく巨大化して突っ走ってますが、必ずしっぺ返しがある。現在は、その途中の過程でしょう。
ところが悪いことに、アメリカの文化、ディズニーランドとかマクドナルドとか、ああいうものにはなかなかしっぺ返しがこない。アメリカの快感原則文化はもろに日本に来たけど、特に日本人の感性としては、外から来たものはみんな神様であるという、つまり外部が自分を律する世界として生きてきた。たとえばコンビニ文化がアメリカから来たら、それを無条件に受け容れてしまう、そういう人の良さというか、こういうものが日本の感性なんです。まあ、タイ、韓国など農耕民族全般に言えるのだけれども、雨を待って、太陽を待ってというように、要するに自分の力ではどうにもならない、外部に支えられるという感性がある。特に日本人は、本来情緒的な民族であって、情緒の皮をめくっていったら最後まで情緒しかないといった民族なんです。
20年前に旅から帰って来た時、「感性」を信じてはいけない、と僕は言っていた。「本音か建て前か」という言葉があった時代で、建前は嘘臭い、本音で行こうみたいな。でも、僕はその時点で建前でなくてはいかんと言っていた。それは理性ということです。既存世界がこれだけ崩れた以上、本音だと全部そっちに行ってしまうけれど、本当は理性が必要なんだと。
アメリカの全能文化に対抗できるのは、イスラム文化だと僕はその頃言っていた。自分の中に非常に強固な核を持っているという意味で。コーランが正しいとか正しくないとかではなく、自分の中に理の力を持たなければ人間が崩れる。
B ─ 未来はどうなるとお考えでしょうか
その質問は愚問かもしれないね。本当は何が起こるかわからないじゃない。目の前の事、一歩前のことを考えれば、それは将来の事を考えているということです。目の前のことだったらすぐに足を踏み出せるけれど、何十里先に踏み出そうとすると、立ち止まって引きこもってしまうよね。今の若い人は割と先を考えてしまう。年金問題なんかその典型だね。20代の子が40年後のことを一生懸命考えて不安がっている。 これはまずいと思うんだよね。
今は雑誌の中に必ずといっていいほど占いコーナーが無くてはならないという時代になった。結局今は、未来、将来のことを考える人間の病、これにますます犯された時代です。僕が会う、悩んでいる子というのは、だいたい将来のことを考えている。
B ─ 先ほどの詰め将棋になってしまうということですね
こういう時代は、遠くのゴールの旗を見ようとすると、引きこもらざるをえない。引きこもる人はどうしても遠くを見てしまうんだね。将来、未来とか。生きている子の 波動・現実は、将来と今のせめぎ合いじゃない。一歩先だけを見たら、人間は楽になって行動ができる。遠くを見ていると行動ができない。
B ─ エッジは今ここにある、ということですか
そう。もうここが将来なの。僕なんか、考えることと行動が同じくらいのスピードだね。遠くを見ないから。だから、気楽に足を踏み出せるし。
B ─ 藤原さんご自身も、次に自分は何をやるのか、楽しみにされているのでしょうね
そう、俺は次に何やるんだろうと楽しみにしているよ(笑)。仕事とは違うけど、最近はボートの免許を取ろうと思っているんだよ。俺は海がむちゃくちゃ好きで、子どもの頃は、よく関門海峡を親戚の船で走っていた。だから、自分でもいつか船を運転して遠出したいと思っていた。乗る以上には遠出をしたい、大きな船ではなく、ぎりぎり小さな船で、外洋に出たいと思っている。それには1級の免許が必要なんです。この歳で、海図の勉強やら難しいことをしなくてはいけない(笑)。
そして、コンソール(運転席)がポンとあってオートバイみたいな船で外洋、大島くらいに行きたいと思っている。外洋には、4メートル級の波があることを想定しなくてはいけなくて、でもキャビン付きクルーザーなんかではなく、風と波飛沫を受けて飛ばしていくのがいい。日本の船はやわだからね。アメリカの沿岸警備隊が使っている頑丈な船があって、そんなのがいい。
B ─ 海に出て、何をしますか?
まずやっぱり大きな波に乗りたい。その船は海面よりデッキが低い。それで、わざわざ入り込んで来た波をポンプで出すということをするのだけれど、安定性と体感速度が普通の船とは、倍違うんです。真鶴で初めてその船に乗せてもらった時、15分くらい走った後に、突然船長が、「藤原さん、あなたはさすがですね」って言うんです。何がって聞いたら、「あなたは一度も後ろを振り向かない。素人を乗せて岸から10〜20分も沖に向かって走ると、何度も岸の方を振り向くものだ」って言うんです。どこか不安を感じるので安全確認をするものなんですね。そういう所を、その人はちゃんと見ている。それを聞いて、「あ、俺は海に合っているんだ」って。試しにちょっと運転させてもらったけれど、「三百人の人を乗せた中で、あんたみたいにスピードを出す人はいなかった」と言っていた(笑)。大きな船だと波に対して突っ込んでしまうけれど、小さな船だと波に対して柔軟に行ける。
海はむちゃくちゃ大きいから、対抗しようとしないで、波に乗らなくてはならない。手に入れようとしている船は、それに対応できる造りになっている。俺はアメリカはあまり好きじゃないけれど、アメリカ人は時々たいしたものを作る。クラフトマン魂があるんだね。
B ─ また、その体験から、どんなエッジが現れてくるのかが楽しみです。
どうもありがとうございました
藤原新也(ふじわら・しんや)
1944年、福岡県生まれ。東京藝術大学絵画科油絵専攻中退、以来、世界各国を旅する。インドを皮切りにアジア各地を旅して、『印度放浪』『全東洋街道』などを著す。第3回木村兵衛賞、第23回毎日芸術賞などを受賞。写真家、作家、旅人。著書に、『東京漂流』、『メメント・モリ』『乳の海』『千年少女』『末法眼蔵』『俗界富士』『なにも願わない手を合わせる』他多数。
オフィシャルサイト
http://www.fujiwarashinya.com/
※インタビューは当時のものです。
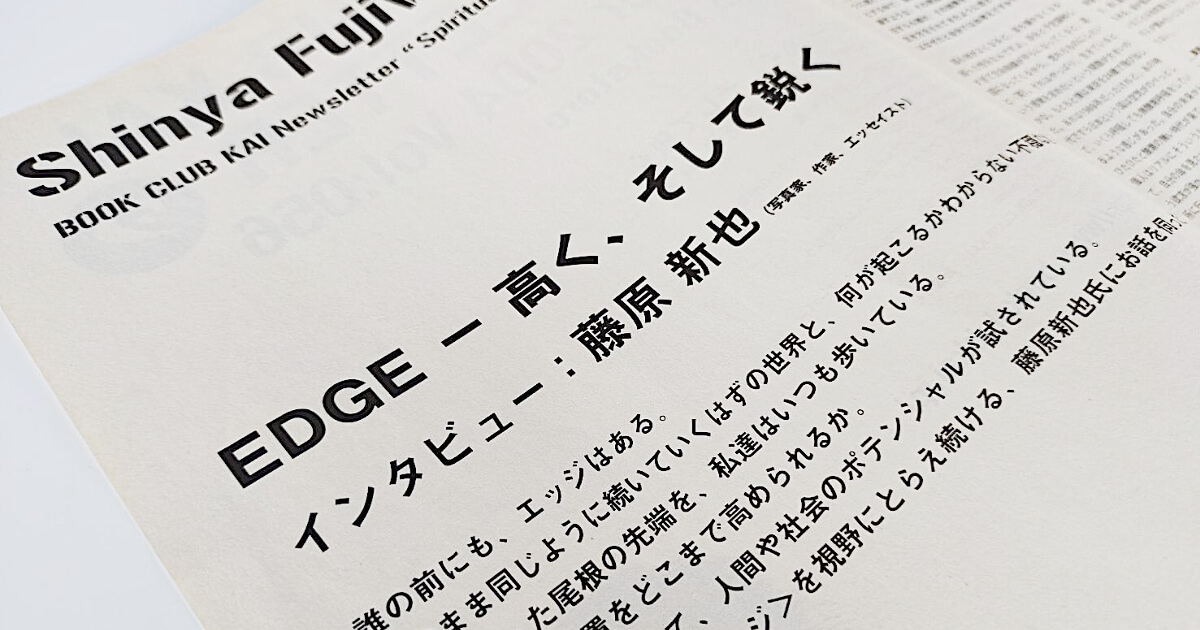
Related Book's
関連書籍紹介
印度放浪(合本)
藤原新也
朝日新聞出版
1100円(税込)
23歳の時、青年はインドへと旅だった。生と死が混在する土地で、彼が見たものは何だったか。旅日記であり、心の記録である本書には、誰もが一度は帯びるであろう、青年期の熱気に満ちている。旅青春論の原典として静かに読み継がれてきた藤原新也の処女作。
メメント・モリ
藤原新也
三五館
1980円(税込)
書名の「メメント・モリ」とは「死を想え」というラテン語の宗教用語。生の光景に潜む無限の死の様相が、極彩色の写真と短い言葉によって、私たちの眼前に出現する。「ニンゲンはイヌに食われるほど自由だ」とコメントのつけられた写真は、あまりにも有名。
東京漂流
藤原新也
朝日新聞出版
1320円(税込)
インドを皮切りにアジア全土を放浪しつくした後で著者が見た東京とは?大都市の裏側で豚は夜運ばれる。舞台を日本に移して現代社会に向き合った著者の鋭い視点が冴える。迷走する日本という国を予見する80年代初頭を飾った大ベストセラー。





