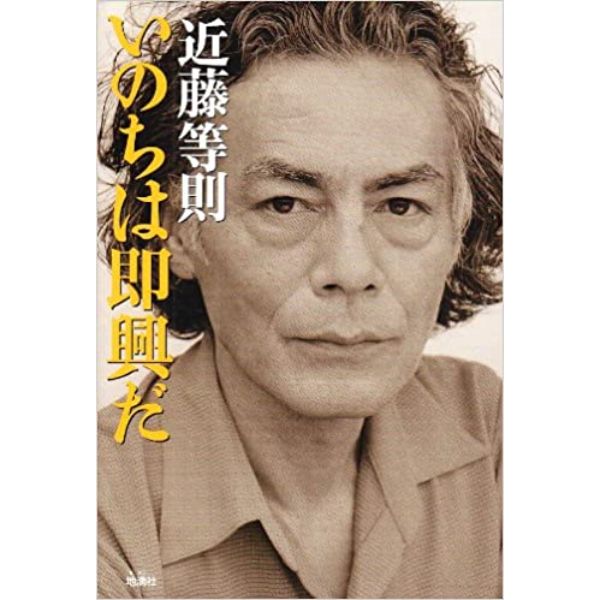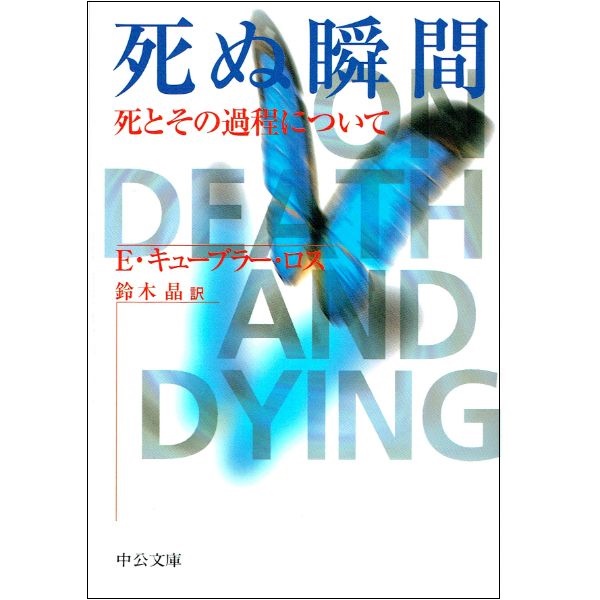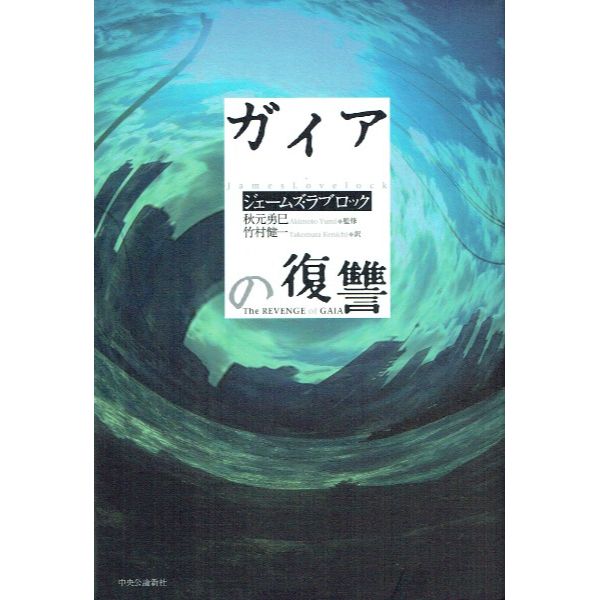『Interview Archive』は、
『NewsLetter』に掲載されたインタビューです。
今回のインタビューは、2001年に行われたものです。
予めご理解のうえお楽しみください。
Interview Archive #23
内と外を繋ぐ音
近藤等則 / トランペッター、音楽プロデューサー

物事を何か立ち上げようとする。そうするとそのセンスにピンときた人が自然に集まり、ひとりでは出来なかったことが、実現に向けて動きはじめる。
近藤氏の呼び掛けは、世界中の一流ミュージシャンに届き、一つの大きな動きとなろうとしている。アンビエントとフューチャー、アナログとデジタル、そこでの共通言語は「音楽」だ。音楽の魅力は語り尽くせるものではなく、いかに発信するかがキーとなり、またそれを届けたいと願う気持ちが大きなエネルギーになるのだろう。
B:近藤さんの音楽活動は個性的で、ジャンルや国を越えて活動なさっていますね。
中でも「blow the earth」 というものがあったそうですが、それはどのような活動だったのですか?
「blow the earth」は、人がいない大自然の中で、僕の電気トランペットのシステムを持っていって、その大自然のバイブレーションを感じたままに即興演奏で吹いてしまうというものです。観客は空だったり、海だったり、山だったりね。
B:その時の演奏はCDやビデオなどになっているんですか?
うん。NHK-BSでイスラエルとアンデス山脈の演奏が放映されました。その後、ドイツの映画監督と一緒にヒマラヤでやったんだけれど、それはまだ発表されていないです。日本では沖縄の久高島や富士山、大島でもやりました。
B:音楽は人と共有することが楽しみの一つではないかと思うのですが、人の居ない所で演奏するというのはどのような感じなんでしょうか?
僕は人間の魂というのは、人間社会だけに所属しているのではないと思っているんです。今でもそんなに変わっていないと思うのですが、バンドをやっていた当時1992~93年頃の日本は、人間がただ人間社会の中で生きているだけの狭いイマジネーションみたいなものが僕の中でキュウキュウしていた。例えば南国なんかはもっとノビノビしているはずだし、そんな場所でなくても、人間の魂はもっと自由なはずだと思うんです。もっと具体的なことを言えば、ミュージシャン同士が集まっても、CDが売れる、売れないの話になってしまうし、レコード会社の人と会うとやっぱり音楽とお金の話になるんです。それがもう、どうしようもないくらい、嫌になってしまったんです。
別にお金の為に音楽やっているんじゃないよというのが僕の本心だから、これ以上は付き合いきれないってね。その頃は人前で演奏するのも一通りやったので、今度は何が楽しいんだろうと考えました。まだ地球上の何処かに、人間が登場する以前のバイブレーションを残した場所があるんではないか、もし、そういう場所があるんだったら、そこにチューニングを合わせて、自分が思い付くままにラッパを吹いてみたいなと思ったんです。僕はずーっとインプロビゼーション(即興)だったので、そういった場所の中では媒体、メディア、霊媒という役割になるんです。
B:そこに行き着くまでにはどのようなことがあったのですか?
音楽というのは感動を伴うものです。自分が20歳の時にミュージシャンになることを決めたんですけれど、その瞬間、奈落の底に落とされたんです。どういうことかと言うと、よし、これからいっぱい練習してミュージシャンになろうと決めたはいいが、僕がラッパを吹いて人に感動してもらえる部分が、自分の中に何もないことに、今さらながら気づいたんです。
あの当時、20歳の僕は黒人のように人種差別された訳ではないし、そんなに不幸な生活をしていた訳でもない、トランペットの能力といったって、たかが知れている。じゃあどうやったら僕の出した音で人を感動させることが出来るのか、と自分の中を色々探したけれど、全然見つからないことに愕然としたんです。
僕は中学1年の頃からラッパを吹いていて、良質なリスナーではあったんですが、「やる」側の人間ではなかったと、また今さらのように気づいたんです。「やる」側の人間と「聞く」側の人間の間には、古臭い言葉でいうと三途の川が流れていて、この川の向こう側に行かないと、僕はミュージシャンとして一人前になれないなと思ったんです。で、どうやったら三途の川の向こうに行けるんだろうと考えたんです。工学部だったんで、そこは理屈で考えました。
それで、近代的トレーニングをやったり、ヨガをやったり、新体道、玄米菜食、瞑想など色んなことを始めてみたんです。もちろん色んな本も読みました。でも、ミュージシャンでラッパを吹くということは、ヘッド(頭)だけではないので、危険なことをしてみたり、様々なことを20代の頃はやってました。
B:先程のインプロビゼーションというのは、やろうと思ってやれるものなんですか?それとも、ふとした時に自然に身体が動くというものなんですか?
子供の時からクラシックや色んな音楽を聞いたんだけれども、やっぱりジャズが一番かっこいいなと思ったんです。中学の時は岩国の米軍基地の放送をトランジスタラジオで聞いていたんです。まだビートルズが『マイ・ボニー』というスコットランド民謡を歌っていた時代です。でもやはり黒人のやるジャズがかっこよくて。ジャズの本質はインプロビゼーションですので、入りはそこです。でも、すぐにインプロビゼーションは出来なかったですね。19世紀の終わりまでは、西洋クラシック音楽が世界をリードする音楽だったけれど、あれは指揮者が指揮して、作曲された曲を演奏するという「作曲」と「コントロール」=統制という音楽だったんです。そして20世紀になると、色々広がりを見せて、コンダクターも居ない「即興」と「グルーヴ」という要素に変わったんです。まあ、どちらがどうとは言い切れないですが、命の本質に近いのは、即興でありグルーヴだと僕は思います。ノリといいますか。で、あの当時、「等価値変換理論」というものがあって、それは一つの山を極めたものは、他の山も分かるという理屈なんです。
僕はやらなかったけれど、学生運動のさなか教授たちを「専門バカ」と言って、吊るしあげていた生徒もいた時代です。しかし、一つの専門を極めたものは、他のことにも転換できるということに共感を感じました。僕はミュージシャンとしてスタートが遅かったので、音楽だけをやっていてもトロい。他のことも音楽に持ち込んで、精神世界だとか、新体道だとか、あと極端にセックスもそうですよね。あれもコミュニケーションだし。客とミュージシャンは男女の関係だとするじゃないですか。そうするとラッパ吹くのもいいけれど、女の子に対しては百の言葉を投げかけるよりも、手を握ったほうがより感じが伝わり情報も伝わりますよね。だから、ある時はラッパ吹きながら突然客席に降りて行って、どうせ抱きつくんだから一番可愛い女の子に抱きつくんです。そうすると、お客さんが100人いようと、何千人いようと、僕にとっては全部で一つの人体なんです。で、その人体に音で触れるのもいいけれど、実際に触ってみた方が早い部分もあるので、触ったらどう反応するかというのもチェックしたりするんです。一人に触るとそのバイブレーションが全体にわーっと広がることがあって、なるほどこういう仕組みになっているのか、と実験してみました。
それと、トランペットの「音」は一番後ろの客席まで届くだろうけれど、「音」に乗っているエネルギーが届いているかどうか非常に不安な時期があったんです。そういう時は演奏が始まる前に突然ぶらっと一番後ろの客席まで歩くんです。そうして後部座席の何人かと会話しておいて、ステージの上からそのお客さんに向かって吹くんです。そうすればその間のお客さんとも繋がるんではないかとか、話せばキリがないくらい、物凄く実験をしていました。音楽を音楽でしか捉えるのではなくて、音楽というものが一つのエネルギーの交信作用だとすると、他のことでチェックしたものを音に焼き直すということですね。
実験の一つで、電車の改札を出る時にノーチケットで出る練習をするんです。勿論お金がなかったのもありますが、普通捕まりますよね。で、そこで極意を学んだのは、「もう出た」と思って歩くんです。「もう出てるんだ、僕は」とね。そうすると一回も捕まらないんです(笑)。まあイマジネーションの練習ですね。20代の後半は毎日瞑想をしていて、次の日のコンサートのことが全部見えるようになって、イメージがクリアにならない時はどんなにラッパの調子が良くても、次の日のコンサートはあまり上手く行かないことがあったんです。「あれ?明日のことはもう今日に決まっているのか?」と思った瞬間に、瞑想するのが嫌になってやめたんです。
で、次に発想したのが、明日のコンサートは終わった所からやるしかないなと考えたんです。前の日に発想されて出来上がったものは、当日、徐々に組み立てていって最後に盛り上がるということですね。でも、盛り上がって一緒になった所から始めるコンサートを発想するんですね。女の子とデートの時も普通は過程があって盛り上がっていきますよね。でもいきなり盛り上がった所からスタートするのがいいでしょ?2時間一緒にいて、初めて盛り上がるというのはフリーミュージックではないと思うんです。奴隷ミュージックに近いですね。でも、人間というのは、生まれた時から祝福されていると発想すると、もう生まれた時から繋がっているのに、なんで2時間もかけて繋がろうとしなくてはならないのでしょう。ベースにまずフリーで繋がっているのだから、そこをスタートとして、あと2時間どうやって演奏するという発想ですね。
B:近藤さんは近々、広島の宮島で行なわれる「聖なる音楽祭」のプロディースをされていますが、こういったことを踏まえて行動しているんですか?
そう。そして終わった後、僕がお金を持ち逃げするんです(笑)。それは冗談として、今度の「聖なる音楽祭」はゴールはないんです。普通、プロのプロモーターみたいなのが行なう時には、始めからゴールがあって、それに向かって組織作りをして軍資金を用意して「よーい、どん」で始めるやり方でしょうけれど、僕達は「何もない所からいける所までいこうよ」という作業だけなんです。もう他力の極地、武術で言えば無刀流。刀を抜かずにどこまで戦えるかという。刀を抜きたくても竹ミツだからね。これじゃ抜けないよね(笑)。
B:一番苦労されていることはなんでしょうか?
自分自身の中に、イマジネーションと集中力がなくなった時ですね。これがある間は苦労はないと思う。もうちょっと言うと、人生で問題が起こるとしますよね。それをネガティブに捉える人はもったいないと思うんです。問題が起こるということは、次にステップアップする最大のチャンスだからね。例えばアフリカのサバンナを250㎞でビュンと飛ばしたら、初めは興奮しますが、常にこの速さだと飽きてくるんです。50㎞の速さと変わらなくなるんです。アインシュタインのe=mc2と一緒で、速さの強弱がないと、エネルギーは発生しない。問題というのは、ある速度で走っていた人生に対してスピードチェンジしなさいよというメッセージでもあるんです。そうすれば次のゾーンに行けるわけですので、「聖なる音楽祭」は面白く取り組んでいます。
B:この「聖なる音楽祭」で伝えたいことを教えてください。
今迄の会話に出てきたけれど、人間の魂というのは、やっぱりフリースピリットだからね。その人間社会に所属しているだけが人間ではないでしょ。もっと大きなものに所属しているというのが命の本質な訳だから、「聖なる音楽祭」は、ある種の自然のバイブレーションを意識し、音楽や人間の行動を通じてどこまでリンクできるか?という試みでもあるんです。「聖なる音楽祭」のサブタイトルも「global quest for unizon」といって、どうやったらグローバルな調和ができるか皆で探求してみようという意味です。「let’s have a journey」でも「let’s have a trip」でもいいから、そういうことに共鳴する人は是非とも宮島に来て欲しいと思っています。
21世紀は人間と自然が調和した時代にならないといけないと言われていますが、僕達日本人の遺伝子の中には、自然と調和するという情報が入っているんです。戦後、特にこの30年間極端な経済活動をしてきたから忘れている部分もあると思うんですが、その会場になる広島の宮島、厳島神社というのは、ちゃんと日本人の遺伝子を証明している所です。あの宮島という瀬戸内海の神様の島に、平清盛が人工的な建造物を建てたんです。でも都会にあるようなものではなく、自然と調和するように作られているから、800年近く残っているんです。世界で有数の経済大国になった今の日本の建物の中で、800年残るものは一切無く、持って100年くらいですね。
もうちょっと言うと、お釈迦様が2600年程前にインドに登場して、「空」という仏教理念のコンセプトをたて、それが中国に伝わって老子、荘子のいた頃「無」になる。そうして、その理念が日本に来た時には、「自然」となるんです。各民族によってとらえ方は色々あるけれど、僕にとっては「空」=「無」=「自然」なんです。そのくらい日本人は「空」の意識や「無」の意識を自然の中に感じているんです。だから、松尾芭蕉の俳句が登場したり、西行の短歌が登場したのです。
例えば芭蕉の俳句にある「しずけさやいわにしみいるせみこえ」というものがありますね。僕はこの俳句は禅の公案だと思っていて、ミュージシャンは一度これについてよく考えなくてはと思っていたんです。蝉の声がギャーギャーいっているのになんで「しずけさ」なのか?「うるささや」だったら分かりますよね。で、「しずけさ」とは何なのだろうなというのが僕の中で問題だったんですけれど、これは要するに、「しずけさ」というのは心の状態をいっているんです。それもただ中途半端なしずけさではなく、なんというかワープしてるんです。この次元の世界から、違う次元の世界に行っている。だからこそ、蝉の声という非物質が岩という物質に染みいって、交流して一緒になっているんです。芭蕉の心は凄まじくイッてしまっているんですね。
もう一つの俳句で「ふるいけやかわずとびこむみずのおと」とあるんですが、この「ふるいけ」が示しているものは、自分の深層意識なんです。アラヤ識よりも深い深層意識にはいった時にあるのが「ふるいけ」なんですね。
B:この「聖なる音楽祭」の話を受けたのはいつ頃なのですか?
1997年の暮れでした。それからよちよち歩きで延々寄り道しながら準備をしていました。僕はこの話が来た時、音楽的な内容については最大限の協力はしたいと思って受けたんですけれど、何回か話している内に僕が全体をオーガナイズすることなっていたんです。最初はチベット・ハウスのラマドゥブーム・トゥルクから話があって、ダライ・ラマに会ったのが1998年の10月でしたね。その後3回ほど会いました。一番最初にあった時は、ヤクザの親分かと思いました(笑)。厳格な雰囲気をだすかと思えば高笑いし始めたりで、全然フィックスされたものが無いんです。いつも同じポーズは全くない。それこそエネルギーの本質ですね。精神世界に傾倒する人の弱点は、ひょっとしてその世界に頼ってしまう場合もあるでしょうが、彼の場合はそういったことが無いんです。去年日本に来た時、テレビのインタビューを受けてて、「癒しについてどう思われますか?」という質問に「癒し?そんなもんないよ。僕のここにデキモノが出来ているんだけれど、治してくれる?」という感じで答えていました。
B:どのような縁だったのでしょうか?
僕が昔作ったバンドの名前の一つに「tibetan blue air liquid band」というのがありました。昔からチベット仏教は興味があったし、4000mを超えるあの場所から見える空の青さは、写真で見ただけでも身震いするくらい凄いなと思います。あの青空の上には真っ暗闇の宇宙があるし、海でも表面は青いけれど、底の方はまた真っ暗闇なんです。人間の精神を見てみても、青空止まりだったら本当の深い所は見えてこない。キリスト教的な光と闇の二元論があって、よく光の方ばかり観る傾向があるけれど、僕は闇の部分もケアしていない宗教は信じられないです。
ミュージシャンだったらわかると思うけれど、グルーヴというのは強弱があって初めてグルーヴになるんです。伸縮しているからグルーヴで、呼吸でも吐いて吸っているからグルーヴになる。片方だけを追い求めても、グルーヴにならないんです。そしてグルーヴは違いだけであって、良いとか悪いとかではなく、一人一人、皆自分のグルーヴをもっている。100年程前にアメリカのミシシッピーデルタで、アフリカ音楽のソフトウェアと西ヨーロッパの軍楽隊のハードウェアがミックスされて、20世紀の音楽がスタートしたんです。そうして100年経ってみたら、不思議なことにジャズやブルーズだけではなく、ロックもパンクもポップスも同じような楽器編成で、同じようなノリを求めた世紀になりました。僕は、21世紀はもっと地球規模でミックスが広がるべきだと思っています。そういう意味で「聖なる音楽祭」は純粋にミュージシャンとして興味があったから、今回の宮島では参加するミュージシャンにいろんなミックスをやって欲しいと思っています。伝統音楽をやっている人同士も共演するべきだし、現代音楽をやっている人も伝統音楽と自然な形で共演して欲しい。どちらかが支配するような関係ではなくやって欲しいんだけれど、それを強制することはやりたくないから、まず最高の雰囲気を作って、そこで出会うなかで自然に発生すればいいですね。
B:全部で何組ぐらいのミュージシャンが来るんですか?
民族音楽だけで、最低10組くらい。本当はあらゆる国から呼びたいんだけれども、そうすると30~40ものグループになってしまうので、今回はシルクロードの辺りのラインを考えているんです。このシルクロードは、ローマと長安の間だったんだけれども、実はイスラエルが一つの分岐点で、シルクロードの商人は基本的にはユダヤ人がずーっとやっていたんです。エルサレムから南下してエチオピアを通じてモロッコ、そして長安から日本の正倉院まで来ています。モロッコの国名の意味は「日の沈む国」ということらしいんだけれど、そこから「日いづる国」の日本との間の音楽を押さえたいと思っています。会場を広島に選んだのは、一つは原爆というのがあります。この原爆というのはこの20世紀間の知恵のまとめ、まあ悪知恵もあそこまでいくか、という感じですが、とりあえず今迄の知恵のまとめとします。そして広島、宮島は21世紀からのオープニングに対するフューチャーがある。宮島には過去と未来が一緒にあるので、理屈でいってもこの場所なんです。
B:以前何かの記事で、近藤さんは「キリストはファンキーなやつだ」と言っているのをみたんですが、近藤さんにとって「funky」という言葉はどのように捉えているんですか?
funkyというのは要するに「人間くさい」ということでいいと思うんです。キリストが僕に「俺こそoriginal mother fuckerだ」と告白したからね(笑)。僕が1981年にイスラエルのエルサレムに行って初めて演奏して、その次の日に教会へ行ってみたんです。そうしたらイエス様が十字架に悲しそうに磔られていて、思わずお祈り中に「イエスさん、酒飲みに行こうよ」と言ったんです。そうしたらイエスさんがびっくりして「俺は2000年間、十字架にかかっていたけれど、お前だけだよ。飲みに行こうと誘ってくれたのは。みんな幸せになりますようにとか勝手な事ばっかりなのに。よし、酒飲みに行こう!」と言って午後3時ごろ、十字架から降りて僕と近くのバーに行ったんです(笑)。そして、当然赤ワインですよねといって赤ワインを注文して飲んでいたらあの青白い顔がほんのりピンク色になってきたんです。僕はハルマゲドンの話しを聞きたかったんですけれど、イエスさんの幸せそうな顔をみていたら聞けなくて、変わりに「マリア様はどんな人だったんですか?」と質問したら、「なんで俺の母親の話をするんだ?」というので「いや、処女でエッチもしていないのになんでイエスさんが生まれたのか知りたいんです」、そうしたら「俺のお母さんの処女膜を破ったのが誰だか知っているか?」というので、その後子供が生まれたという話もあるので、「お父さんですか?」というと「いや、違う」、僕が「誰ですか?」と聞くと「ワシだ」と答えました。「えっ?」、しかも「生まれる時にワシが内側から処女膜を破ったんじゃ」というんです。「ワシこそoriginal mother fuckerだ」といって、また顔色を青くして十字架に磔いたんです。僕はイエス様が十字架にかかっているのはきっとお母さんの処女膜を破ったからじゃないかと思いました(笑)。ツアーとかで、色んな人種が集まり打ち上げで飲んでいる時にこういうジョークを白人に言うんです。面白いですよ。まあ、話を戻して、イエス・キリストが生まれた時、東から3人の男がきて祝福したと聖書にあります。イスラエルの東といったらアジアですね。キリストの教えがキリスト教になったのは西暦100年位にある宗教改革があったからで、その時にキリストの髪が黒色から金髪になって目が青くなったんですが、もともとイエス・キリストはアジア系だったようです。イエス・キリストは10代の半ばから20代の後半まで行方不明だったけれど、その間、エジプトを通じて、インドあたりまでいって勉強してきたと僕は思います。当然、あの当時のイスラエルの商人達はシルクロードでインドまで行けるルートをもっていたので、行きやすかったんでしょう。
B:こういうことが表層に出ないのは何故だとお考えですか?
民族宗教と世界宗教の違いだと思います。世界三大宗教とか四大宗教とか、でかい宗教がありますね。あれは、国家を作る時にああいったものが無いと作れなかったんです。
違う部族をまとめて国家を作るためには、精神的なことを統一することが必要になってくるんです。ヨーロッパだって、キリスト教が入ってくるまではドルイド教というものがあったんですが、これはケルトが元ではなく、実はドイツのライン川の中流から発達したみたいです。まだこの辺の古い家とかには、自然の草木をモチーフとした飾りがついているんです。神道も、アメリカインディアンも、南米のインディオも、アフリカの宗教もそういう自然を崇拝する意味では、凄くよく似ているんです。でも、統一をするために世界宗教というのを登場させて、変えていったんです。イエス・キリストなんて、実は、サドゥーみたいな人、今で言えばある種のヒッピー的な人だろうし、いずれにせよ自由な精神で、一人で動いていた人で、組織を作るのにキュウキュウしてなかったんです。エッセネ派の死海文書も、核心の部分は今でも封印されていますよね。しかし、何時の時代でも、体制側と反体制、例でいえばチベットを中国から返還するというフリーチベットという運動があるんですけれど、実際にはダライ・ラマ本人は好きではないんです。放っておいても帰ってくるものを、なぜ騒いでいるのかというスタンスらしいです。今の社会で禁止されているものだって、上のお偉いさんの都合で禁止にしたのだが、時代は変わっているんです。ビジネスで禁止したものはビジネスによってやんわり変えるというのが、お偉いさんの発想だからね。でも、世の中でもなんでも、変わる時には突然変わるものだと思うんです。y=axみたいに正比例で変わることなんてありえない。今の社会をみても、急激に変わらざるをえなくなってきて、あらゆる問題が発生しているけれど、これらは変わるためだからね。もう、一世代、20~60歳まで毎日、背広着て同じタイムスケジュールで動いていたら人間の体や精神はボロボロになるということが分ってしまたんだから、もう二世代、三世代同じようなサラリーマン社会をやったら、民族のエネルギーなんてゼロになることは、誰だって分かります。今はまだ、オールドシステムの方が強いけれど、時間の問題ですね。「聖なる音楽祭」をやっていて、自分の足であちこち歩き回って色んな人の話を聞いていると、今は凄い変わり目の時期だから、僕たちみたいのがこういうことをやっても、何とかできるんだなと思います。3年前は、こういったボランティアのシステムで「聖なる音楽祭」は出来なかったでしょう。しかし、無理をして変わるというのは、変わったとしてもまたイビツな変わり方になるんです。無理と道理の違い、道の理屈というのがありますが、「道理でねえ、ああそうか」という感じでないと違う無理になってしまう。道の理屈にあっている事は、あとで皆が「道理でねえ」と思うんです。
B:近藤さんは、現在アムステルダムに本拠地を置いて音楽活動をしているそうですが、ずばりアムステルダムはどんな所ですか?
あそこは運河が多く、その周りには緑もあり自然な時間の流れがあります。そして毎日毎晩、「行ったり来たり」出来る場所ですね(笑)
B:本日は興味深いお話を、どうもありがとうございました。
近藤等則(こんどう としのり)
1948年~2020年 愛媛県出身。1983年東京を発信源としたバンド「近藤等則IMA」を結成し、93年まで世界中でライブをこなし活躍する。IMA解散後、活動拠点をアムステルダムに移し、大自然の中でエレキトランペットを吹くプロジェクト「地球を吹く」をスタート。イスラエル・ネゲブ砂漠やペルー、アンデス山脈などで地球や自然のヴァイブレーションと共演。常に新しい音を模索して活動していた。
近藤等則 Official WebSite
https://www.toshinorikondo.com/
Related Book's
いのちは即興だ
近藤等則
地湧社
1870円(税込)
「死ぬ時をイメージしたら、笑いながら死ねる音楽の道に進んだ方がいいと思った」。トランペッターである著者の志望動機である。大自然の中で即興演奏を続ける現役60歳、快楽主義者が放つエナジー。自分なりのスタイルをみつけたいとき、手にとりたい一冊。
死ぬ瞬間
死とその過程について
E・キューブラー=ロス
中央公論新社
1152円(税込)
近藤氏がミュージシャンになることを決意したのは、自分自身の死の瞬間を想像し、この道だったら笑って死ねると感じたからだという。誰でも経験する死。この本の著者は末期医療の現場をレポートし、死に到る人間の心の動きを5段階に渡って解説している。
ガイアの復讐
ジェームズ・ラブロック
中央公論新社
1760円(税込)
地球は生きているという考え(ガイア理論)に基づいて地球を診断し、人類によって壊されてゆく、絶妙に保たれてきた地球の現状と、その再生へと向けて、科学的見地にたって治療を施す。この意図は、地球のために演奏する姿と重なる。