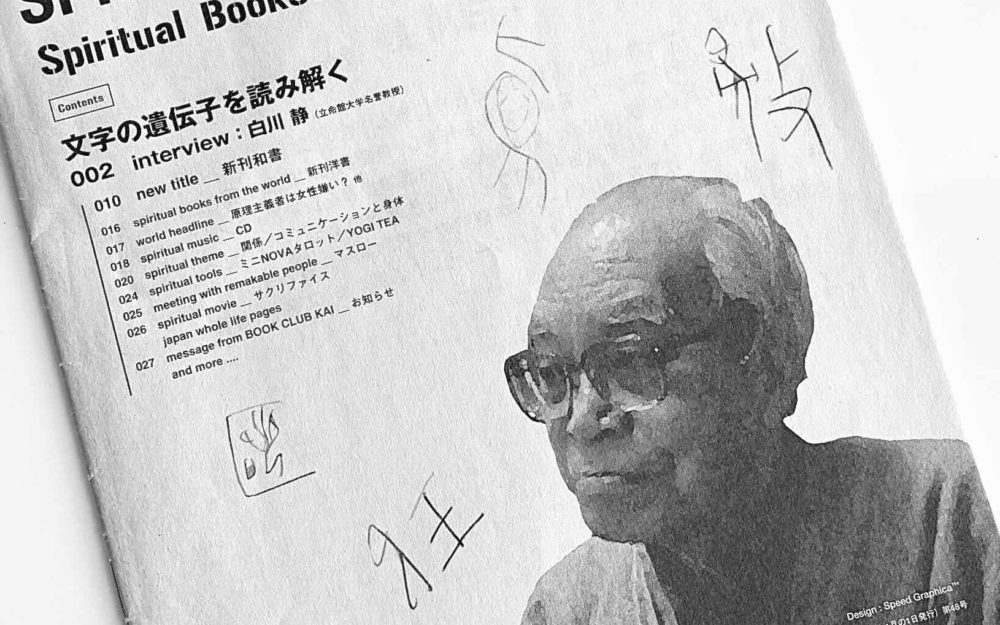Meeting With Remarkable People #23
プラトン
B.C.427 - B.C.347
ギリシアの哲学者。ソクラテスの弟子として知られる。アテナイ市外に学園(アカデメイア)を開いた。イデア論に基づいて、認識、道徳、国家、宇宙の諸問題を論じた。
「ところで君も知るとおり、どのような仕事でも、その始めこそが最も重要なのだが、何であれ若くて柔らかいものを相手にする場合には、とくにそうなのではないかね? なぜなら、とりわけその時期にこそ形づくられるのだし、それぞれの者に捺そうと望むままの型がつけられるからだ。」
『国家』より

かつて人は、自然を哲学の対象とし、世界の根源を「火・水・空気・土」などと考えた。しかし、その世界を認識するのは自分たち人間である。そのため、人間の心理や論理についての思索こそが「真理」発見の鍵である、という考え方にやがて移り変わってゆく。そのような流れを生みだしたのがソクラテスだとすれば、その哲学体系を緻密に作り上げ、本格的な著作の形で最初に記したのがプラトンである。
紀元前427年、ペロポネソス戦争が始まって間もない頃にプラトンは生まれた。彼の家は、アテナイの名門であった。その一門には歴史的に有名な人物が多い。母ペリクティオネの血筋は、民主政治の祖ソロンにつながり、父アリストンの家系は、伝説におけるアテナイ最後の王コロドスにつながるといわれる。彼は名門の生まれに相応しく、高い教育を受け、絵の勉強をし、叙情詩や悲劇も書いていた。早くから政治的な指導もあったようだ。こうした背景から、彼は早くから精神的に開かれていたことが窺える。少年期で道義心を確立し、哲学者の道へとまっすぐ一直線に進んで行ったようだ。
プラトンの青年期は、戦争と祖国が次第に衰退してゆく時期に重なる。18歳頃から5年間、軍務に服していたとも伝えられる。彼の人生を決定づけた「ソクラテスとの邂逅」は、この頃である。劇場の前で演説するソクラテスの言葉が耳に入った瞬間、彼はその場で、手に持っていた書物や詩集を焼き捨ててしまった。そしてソクラテスに向かって、「弟子にしてください」と懇願した。プラトンはその後約8年間、ソクラテスの最愛の弟子として人生を過ごした。
紀元前401年、26歳のプラトンには、まだ政治家になるという志が残されていた。しかし、28歳で経験した「ソクラテスの刑死」が引き金となり、哲学の道へ進むことを決意する。哲学者が職業として認められていなかった時代に、プラトンは師の遺志を守るために、自ら厳しい生活を選び取ったといえる。政治的な理由による危険回避のため、メガラ、キュレネ、エジプトなどを遍歴。この頃より、ソクラテスを主人公とするいくつかの書物を対話形式で書き始める。
「ポリテイア(理想国)」の構想を進めてはいたものの、実践的政治活動には決して足を踏み入れなかった。「何を行うにも、哲学が根底になければならない」という堅い決意があった。この頃、プラトンの中に確立されていたのは、「哲学者が政治をするか、政治家が哲学をするかしない限り、人類は救われない」という思想だった。これは、後に著作『国家』や『法律』の中でも表明されている。
プラトンがソクラテスの二番煎じで終わらなかったのはなぜか。ひとつには、芸術的素質があったことが挙げられる。その感性が結実した「イデア論」は、彼が編み出した哲学の中で、最も美しい孤高の業績であった。理性によってのみ認識されうる実在、永遠不変の価値を「イデア」と呼び、それに基づいて論じた認識、道徳、国家、宇宙についての思索は、どんな哲学者とも違う未来を描き出した。そして、もうひとつの理由は、プラトンに現実を配慮する精神が培われていたことである。
「哲学者の任務は、イデア界を認識して、現実の世界をその理想世界に近づけること」という自身への課題は、アカデメイアの創立に結実する。アカデメイアは、学問の府として900年近く存続し、多くの政治家、哲学者、数学者、天文学者を育て学問の世界に金字塔を打ち立てた。
生涯独身を貫いたプラトンの晩年は、孤独に満ち、とても静かだった。しかし彼の愛知活動への情熱は、決して途絶えることがなく、外見的な穏やかさとは裏腹に、胸の内では「知」の炎が燃え上がり、いつも哲学的葛藤が繰り返された。最期の最期の瞬間まで、ペンを握っていたと伝えられるほどであった。公表された彼の著作は古代哲学の著作としては例外的に、ほぼ完全な形で今日に残されている。