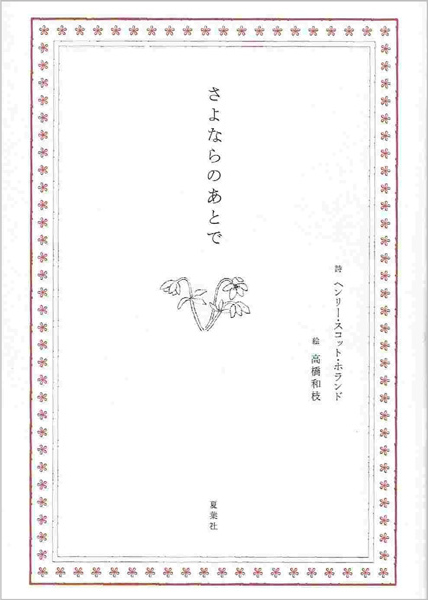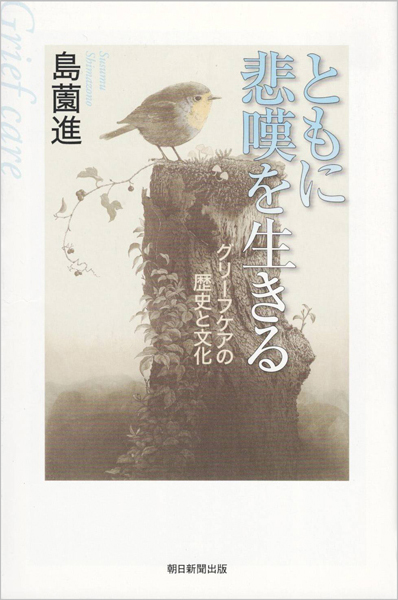死は万人に訪れるとはいえ、早すぎる死は遺された者たちにとって受け止めがたい現実だ。
イギリスでは1982年、子どものためのホスピスが始まったが、日本に入ってきたのは、まだ十数年前のこと。
2024年、子ども家庭庁がこどもホスピスの全国的な支援を決め、ようやく全国に広がる流れが整い出したばかりだ。
そこで、大阪に次ぐこどもホスピスである「横浜こどもホスピス〜うみとそらのおうち」の設立に奮闘した代表理事の田川尚登さん(たがわひさと)にお話を聞いた。

我が家のように
玄関の扉をくぐると、花瓶に活けられた明るい色合いの花々が目に飛び込んできた。
「ここのデザインは、自然とのハーモニーがテーマです」という田川さんの言葉通り、さくらや藤、空色など、自然の景色にある色彩がデザインの基調に据えられている。大きな窓がそこかしこに設けられた見通し抜群の空間は、外からの光に柔らかく満たされている。窓の向こうには空と水が一面に広がり、すっぽりと自然に包まれているような感覚におちいる。
「ホスピス」と聞くと、一般的には医療施設を連想しがちだが、ここ「うみとそらのおうち」は、生命に関わる病いを抱える子どもとその家族が、我が家のように利用するための場だ。子どもでなくともワクワクしてしまうような仕掛けや遊び道具がたっぷりと用意されている。
大人向けのホスピスは、痛みを緩和する医療ケアが中心となるが、子どもの場合、やりたいことを叶えることを重視する。子どもたちは、命のともしびが消える直前まで、生に対して積極的に向き合っているからだ。
「大人には振り返る過去もたくさんありますが、子どもたちは成長発達の過程です。そんな子どもたちが『生まれてきて良かった』と思えるには、本来の成長発達に応じた遊びができたり、好物を食べたりして、家族と一緒に楽しく過ごす時間が一番大切なのです」と、田川さんが説明する。さらに、「それは親にとっても重要なことです」と言葉を継いだ。遺された家族は、喪失という辛い経験を乗り越える必要があるからだ。楽しい思い出を積み重ねれば重ねるほど、立ち直る力につながる。それが、多くの家族を見守ってきた田川さんの確信だ。



本音で話せる関係性
実は、田川さんがこのプロジェクトを立ち上げたきっかけは、1998年、当時6歳だった次女を悪性脳腫瘍で約5ヶ月の闘病生活の末に亡くしたことだった。
最期は脳死状態となった。我が子の容体は日を追うごとに悪化し、人工呼吸器を外すという苦渋の決断を迫られた。亡くなった直後こそ、苦痛から解放させてやれたと安堵したものの、次第に自分たちの判断が正しかったのかという思いに苛まれ、なかなか前向きになれずにいた。
「私の場合、立ち直るのに4年半ほどかかりました」と、田川さんは振り返る。
この体験を通して、当事者に必要なものが見えてきた。
「医療施設は病気を治すことが主眼なため、どうしても子どもの成長発達を抑えつけてしまいがちです。医療にできない部分だからこそ、最期まで子どもらしく過ごせる場を作ることが必要なのだと気付かされました。『小児医療を改善してほしい』という娘からのミッションと捉えて、取り組んできました」
また、心のうちを表現することの大切さも痛感したという。
「呼吸器を外す決断をしたときに、助言を与えてくれたり、寄り添ってくれた先生方が何名もいました。しかし、職場では本音を話しにくく、自分を出せる場が限られていたので、乗り越えるのに長い時間がかかりました」
田川さんは言う。「病気の子を抱える家族は孤立している中で生活しがちなので、気楽に話せるような関係性は重要です。ここでは、家族と同じ目線になって一緒に悩むなど、寄り添うことを大切にしています」
初めて利用する家族には、自らキッチンに立って芋煮を振る舞ったり、子どもと家族がコミュニケーションを取る場には、スタッフが必ず一緒に関わるようにする。
「話しやすい雰囲気の中で気を許してもらうようになると、スタッフと家族とのコミュニケーションが深まって、本音で話せるような関係性になります。それは、スタッフが家族との時間を共有しているから、話せるのです。気を遣うのではなく、気楽に来られる場所が、こどもホスピス」と、言葉に力がこもる。
親がくつろいでいるときは、スタッフが本人やきょうだい児と一緒に遊んだり、なるべく一緒に食卓を囲む関係性は、親戚や身内のようだ。
「病院は亡くなったら関係性が切れてしまいますが、ここは亡くなってからも利用ができるので、関係性がずっと続きます。亡くなった子どもの誕生日会を行ったりもしています。私はここで、年齢的にもお祖父さん役なんですよ。女性よりも男性の方が気持ちを吐き出せない場面が多いので、困っている父親のグリーフケアをサポートしています」と、はにかむ。

豊かさは日々の中に
遺族へのアンケートでは、「終末期にどう子どもと過ごしたかったか」という問いに対して、「子どもと同じベッドで眠りたかった」という回答が一番多く、次に「自分の手料理を子どもに食べさせたかった」、「一緒にお風呂に入りたかった」と続く。
「ベスト3の回答がここで全部叶うようにしています」と田川さんが胸を張る通り、宿泊部屋には高さの調整ができる広いベッドが2台並び、車椅子の子どもでも調理に参加できる対面型のキッチン、宿泊部屋の天井から下げられたリフトに乗ったまま入れる大浴槽などを完備している。
容態の急変に備え、近隣の医療機関との連携もしてはいるが、3年余りの運営の中で、救急車を呼ぶ事態となったのは一度だけだという。

「重い病状でも、やりたいことをやり切るという強い想いがあるとき、医療トラブルはほぼ起きないですね。最初にここを利用したお子さんは、『花火がしたい』と花火をして、戻って2日後に亡くなりました。うちの娘も、最期まで家族との楽しい時間を求めていました」と、述懐する。
痛烈な体験を通して多くの気付きを得た田川さんは、きっぱりと言い切る。
「本当の幸せは、普通の毎日を普通に過ごすことです。一緒にお風呂に入ったり、ご飯を食べたり、寝たりすることこそが幸せな時間です。余命が短いと宣告されても、意識をすれば、豊かに生きられるのです」
特別な場所で特別なことをすることだけが、生の豊かさを味わうことではない。
日々の繰り返しの中で、今この瞬間に起きていることや目の前にいる相手にしっかりと向き合うこと。そうすれば、ありきたりの日常というかけがえのないきらめきを受け取ることができるのだ。



広がれ、こどもホスピスの輪
活動を行う中で、スタッフたちが力をもらうのは、利用者家族が元気になっていく姿を見ることだ。
「関係性が途切れずにお付き合いをする中で、きょうだいの成長や、ご両親の悲しみを乗り越えていく姿を見ていくと、やっていて良かったな、と一番思います。ここを利用したことで、短い時間で気持ちの切り替えができるのを見て、家族のように嬉しいです」
一方で、残念に感じるのは、日本ではまだまだこどもホスピスの周知が低いこと。
「ソーシャルワーカーが病院にいたりしますが、本当に家族を支えるところまでいっていないのが現状です。こどもホスピスが全国にあれば、サポートを広げていけます。ここで経験したことをお話しして、力になりたいです」
イギリス、ドイツ、オランダなどのこどもホスピス先進国では、自然な形で皆が手を貸してくれるという体験を見聞きした。
「生活の場や街中に、優しい気持ちがあふれています。日本にも『お互いさま』という考えがあるので、もっとそういう風になっていけばいいなと思います」
そのために『こどもホスピスってなあに?』という冊子を区内の学校に配布して話をしたり、子ども向けの見学会を催したりしている。
自分たちに何ができるかを小学生に提案してもらう取り組みも、去年から始まった。
すると、身体の自由度に合わせた遊びを考えたり、「うみそらっていいな」という歌を作詞したりと、子どもたちの目線からの思いやりが詰まったアイディアが多く寄せられた。
「娘が6歳で亡くなったことがきっかけでこどもホスピスができた、ということをしっかりと受け止めてくれているようでした」。子どものうちから知ることの重要性を改めて実感した。
大人は理念や理想が先立つことが多いが、感性が豊かな子どもたちは、メッセージがまっすぐ心に届くのであろうし、年齢が近いぶん共感しやすいのかもしれない。
日々の暮らしの中にある豊かさを人々がかみしめ、最期まで子どもが子どもらしく生きることを大切にする社会は、真の豊かさを備えた社会だ。
こどもホスピスの活動が、日本中に広がる大きな輪になる日がそう遠くはないことを願いつつ、施設を後にした。
街を吹き荒れていた強い風に乗って、向かいの大きな公園から木々のざわめきと子どもたちの歓声が運ばれてきた。

プロフィール
田川尚登(たがわ ひさと)
1957年、神奈川県横浜市生まれ。大学卒業後、ベンチャー企業、印刷会社を経て、2003年、NPO法人スマイルオブキッズを設立。2008年、病児と家族のための宿泊滞在施設「リラのいえ」を立ち上げる。2017年、NPO法人横浜こどもホスピスプロジェクトを設立し、代表理事に就任。他、NPO法人日本脳腫瘍ネットワーク副理事長。「病気や障害がある子どもと家族の未来を変えていく」をモットーに小児緩和ケアとこどもホスピスの普及を目指している。

関連書籍紹介
ヘンリー・スコット・ホランド / 夏葉社 / 1430円(税込)
自分が亡くなった後、遺した大切な人たちには、悲しまず、幸せに過ごしてほしいと願う。本書は、英国教会の神学者で哲学者の42行からなる一編の詩を、挿絵を添えて一冊の本にしたもの。「死は何でもないものです。私はただ、となりの部屋にそっと移っただけ。」大切な故人からのようなメッセージが大きな悲しみを癒してくれる。
ともに悲嘆を生きる
グリーフケアの歴史と文化
島薗進 / 朝日新聞出版 / 1540円(税込)
宗教学、スピリチュアリティ研究で日本を代表する著者が、近代の日本におけるグリーフケアの流れとその表現を解説する。人がともに生きるというだけでなく、宗教や物語を介して悲嘆をこそどのように生きようとしてきたのか。日本社会におけるグリーフケアの流れを概観していく。