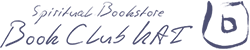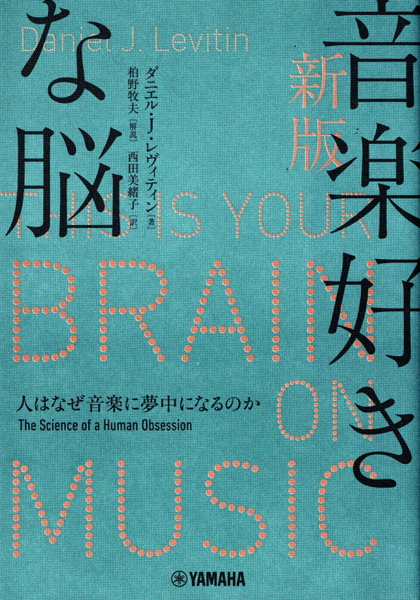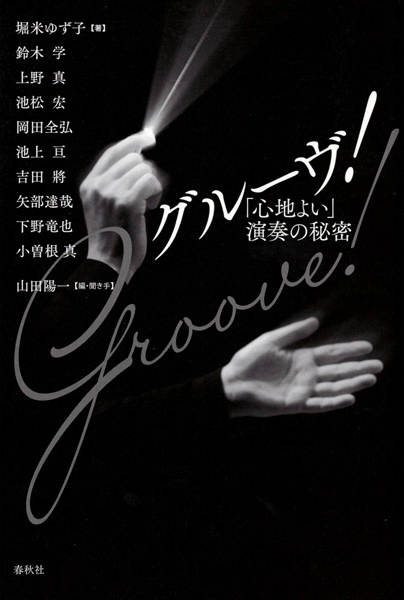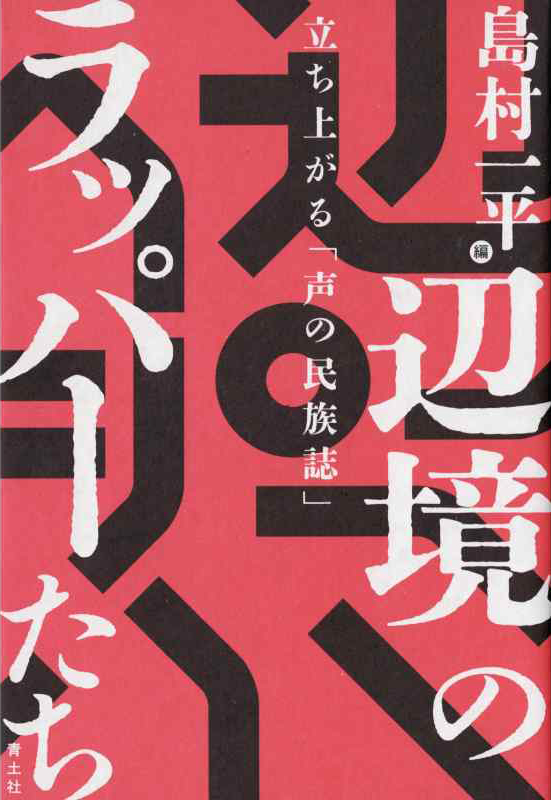レントゲンフィルムに録音されたレコードが
1950〜60年代の冷戦時代にソ連で作られていた。
その名も「ろっ骨レコード」。
表現の自由が制限されていた国で、
密かに大流行したこのレコードを研究している人がいる。
その人、西野肇さんは若き日に単身ソ連に渡り、
音楽は国境を越えることを証明した人だった──。
ろっ骨レコードは 取り締まりの対象だった
ターンテーブルに針が落とされ、ザーザー、ブチブチ、という雑音のなか、タンゴの曲が始まる。甘く切ないバリトンの歌声が響き渡り、なんともいえない哀感が立ちこめてくる。
「これはね『タチアナ』という曲。歌っているのはピョートル・レーシチェンコというウクライナ出身の歌手で、スターリン時代に逮捕されて獄死した人です。かつてのソ連では、みんな隣近所に聴こえないように、こんな曲をこっそり聴いていたんですよ」
そう話すのは西野肇さん。25歳で当時のソ連に渡り、モスクワの放送局でアナウンサーを務めた経歴の持ち主だ。西野さんがレコードプレーヤーで回しているのはソノシートで、よく見ると人間の骨が写っているレントゲンフィルムである。これが1950年代から60年代にかけて、ソ連の市民のあいだで密かに流行していた「ろっ骨レコード」と呼ばれるもの。病院で廃棄物となっていたレントゲンフィルムが使われたことからその名がついている。
「この曲はタチアナという恋人への思いを歌ったラブソングですが、冷戦時代のソ連では、こうしたポピュラー音楽、特に西側の音楽は禁止されていたんです。当時は社会主義を礼賛するようなレコードしか売っていなかった。それよりはこの曲のように、『僕は君が好きなんだ、もう一度会いたい』という歌を聴きたがっていたんですよ、ソ連の人たちは」
「ろっ骨レコード」は、聞くのはもちろん、作っても売っても当局から目をつけられ、懲役刑に処せられた人もいたという。このレコードの存在を知ったのは、西野さんがモスクワ放送局に勤務していたときだった。
「73年から83年にかけてモスクワの放送局で働いているとき、ある人から『誰にも言うなよ。実は、“ろっ骨レコード”というものがあったんだ』と。僕がいた頃はそれを見ることはできなかったんだけど、当時はブレジネフ政権の時代。『ろっ骨レコード』という言葉を発することすらはばかられました」
西野さんは帰国後、テレビプロデューサーとなり、ろっ骨レコードを探索するドキュメンタリーを制作することになる。2000年の頃だ。
「モスクワ放送で働いていた頃の上司に相談してみたんです。そのときはもうソ連は情報公開の時代になっていたので、ろっ骨レコードを持っている人、買った人や作った人がいたらぜひ連絡をくださいと放送で呼びかけてもらいました。すぐ電話がかかってきましてね。持っている人や実際に作っていた人の取材ができ、無事番組にもなりました。いまプレーヤーにかけているろっ骨レコードは、その持ち主がプレゼントしてくれたものです」

ビートルズを冷戦下のソ連で 電波に乗せる
西野さんは、現在「ろっ骨レコード研究家」としての顔も持ち、さまざまなイベントで冷戦時代のソ連の音楽事情を紹介しているが、音楽が国境を越え、人々をつなげるものであることを、身をもって体験している人だ。それは西野さんが25歳で単身ソ連に渡ったときから始まっている。
「僕が若い頃、ソ連のイメージは良くなかった。でもね。だからこそ行こうと思いました。いろいろ言われているけれど、本当のところはどうなのか。だから行けるとなったとき、これは千載一遇のチャンスだと」
西野さんが民放テレビ局でADをしていた72年、日本向けのモスクワ放送のスタッフを募集していると聞き、採用試験を受けることに。西野さん以外に、革新政党から推薦された人や、ロシア語が堪能な候補者が何人かいたが、選ばれたのはソ連とも縁がなく、ロシア語もまったく話せない西野さんだった。
「なんで僕なんだろうと。どうやら、ロシア語ができなくても番組が作れる人が欲しかったみたいです。モスクワ放送局の日本課には、日本人もいましたが、第二次大戦中にソ連に亡命した人たちが大半でしたから、若い血を入れないといけないと思っていたようです。家族や友人にはずいぶん心配されましたよ。でも僕はこれでやっと一人になれる! と。それまで実家から離れたことがなかったので、解放感がすごかった。でも自由を求めたはずが、行った先は不自由な国だったという(笑)」
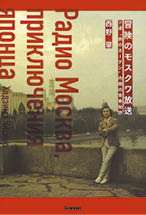
西野肇氏 著書『冒険のモスクワ放送 ソ連〝鉄のカーテン〟内側の青春秘話』 (学研プラス)

モスクワ放送局のスタジオで放送中の西野さんと、共にDJをつとめたガリーナ・ドゥトキナさん。(「エコー」アイスト・コーポレーション発行/1983年vol.2 No.13より)
西野さんが勤めることになったモスクワ放送局は、当時、日本はもとより世界各国にラジオ放送を発信していた。
「ソ連のプロパガンダです。だから聞いていても、『社会主義発展のためにこんなことをしています』とか、『労働組合はこんなに頑張っている』といった番組ばかり。そんなの誰が聴くんだ? と思いましたね。だから逆に、これからどう変えていこうか、やりがいがあるぞと感じました」
西野さんはほどなく、番組の制作をまかされた。そこでひらめいたのが、番組の最初と最後に、ザ・ビートルズの「バック・イン・ザ・U.S.S.R.」を流すことだった。
「日本から持ってきたビートルズのレコードをスタッフに聴かせました。だって『ソ連に戻ろうぜ』という曲ですよ。ぴったりじゃないですか。スタッフは僕とほぼ同世代の若者たちだったけど、ビートルズを聴いたことはなかった。録音室で聴かせたら、みんなの目の色が変わりました。やっぱり好きなものを聴きたいという雰囲気ができつつある頃だったんでしょう」
「バック・イン・ザ・U.S.S.R.」をモスクワ放送の電波に乗せることに成功した西野さん。局からのおとがめはさほどなかったという。
「日本課の上司が僕のところに来て、流暢な日本語で『あれはちょっとまずいです。“ウクライナの女の子といちゃいちゃしよう”なんて歌詞は良くない』と。でもその上司は上のほうには報告せず、自分のところで止めてくれたようです。そのことにはとても感謝しています」
西野さんは、ソ連で初めてビートルズを放送の電波に乗せた人ではないだろうか。その放送は、遠く離れた日本のリスナーにも届き、大きな反響を呼んだ。
「モスクワ放送なのに、ビートルズが流れているとみんなびっくりしたみたいですよ。『モスクワ放送快挙!』とか『西野さんがんばってください!』という応援のハガキが日本からたくさん届きました。僕はある意味、突破口を開いたと思っていますが、まわりのスタッフも、もっとリスナーが耳をかたむけてくれる番組を作らないといけないと思っていたことは確かです」

音楽、そして 歌の力を信じること
西野さんのモスクワ放送勤務は、当初2年の契約だったが、延長につぐ延長で、結果、10年間のソ連生活となった。
「居心地は良かったです。ほんとに。ただ質素でしたね。モノがない時代でビール1本買うのにすごい行列でした。雪の降るマイナス20℃ぐらいのところで1時間は並ばないといけないし、並んだからといって買える保証はなかった。途中で売り切れたらそれでおしまい。でもつらいのはそれくらいです。ソ連、いまのロシアもそうですが、ものすごい多民族国家なんです。ヨーロッパ系の人もいれば、アジア系の人もいる。僕なんか中央アジアのカザフスタンとかトルキスタンの人だと思われて、どんどんロシア語で話しかけられる。片言でも答えれば。向こうもこいつはロシア語をあまり話せない中央アジア人だと勝手に思ってくれるから、それでいいんですよ。そういう意味で外国に対する偏見がなくなりました」
10年間、ソ連で生活した西野さんだが、帰国を決意したのは、母親のことを考えたからだと話す。
「そもそも僕がソ連に行くときに、母と約束していたことが2つありました。それは『2年の契約が終わったら帰ること』と、『結婚は帰国してからにすること』だったんです。でも2年が10年になってしまい、結婚もして子供もできちゃいました。2つとも破ってしまって申しわけない」
そう苦笑する西野さんは、リトアニア出身の女性と結ばれ、家族で帰国を果たした。そして前述したように、テレビプロデューサーとなり、ソ連での経験と人脈を活かしながら数々のテレビ番組を制作し続けてきた。

「これは個人的な感想ですが、ウクライナと戦争をする今のロシアと比べて、自分がいた頃のロシアがいちばん良かった気がします。当時のモスクワ放送局は、若い人の意見や、やりたいことを認めてくれた。モノがなくて規制も厳しかったのは確かでしたが、一緒に仕事をした人たちはみんな温かくて、彼らも、このままじゃいけないと思っていた」
ここまでの話を聴けば、西野さんは、ろっ骨レコードを命がけで聴こうとしていた人たちがいたことに、大きなシンパシーを抱いていることが理解できるのではないだろうか。
「音楽はいろんなものを越えますね。論理じゃないから強い。いったん気に入ったらやめられないんだもの。もう1回聴きたくなる。音楽の力、歌の力は馬鹿になりません。どんなに禁じられても、聴きたいし作りたいし、みんなに聴かせたくなりますから」
音楽の力を信じ、自由の大切さを、遠くモスクワから伝えてきた西野さん。ろっ骨レコードを手に、これからもその精神を伝え続けてくれることだろう。
プロフィール
関連書籍紹介
新版 音楽好きな脳
人はなぜ音楽に夢中になるのか
ダニエル・J・レヴィティン / ヤマハミュージックメディア
¥2090((税込)
私たちの脳は、どのように音楽を受けとめているのか、ミュージシャン、音楽プロデューサーを経て、音楽認知神経科学者に転身した著者が語る脳と音楽の関係。音色やリズム、ハーモニーを聞き分ける時の脳の反応、専門家と愛好家を分かつものは何か、なぜ私たちはある種の音楽に惹かれるのかなど、興味深いトピックに惹かれて読み進んでいくと、複雑に連携しながら音楽情報を処理する脳そのものが、聞いている音楽に共鳴しながら、美しく精妙なアンサンブルを奏でているようにも思えてくる。
グルーヴ!
「心地よい」演奏の秘密
堀米 ゆず子、鈴木 学 他 / 春秋社
¥2970(税込)
グルーブとは何か? ノリ? 体を揺らしたくなるような心地よさ? 改めて聞かれると、考えこんでしまうこの言葉について、民族音楽学者が、様々な楽器の演奏家に話を聞きながら、西洋クラシック音楽に於けるグルーヴというテーマを掘り下げる。 演奏家たちの言葉は、それぞれに多様で個性に溢れていながら、一つの共通点を内包しているようにも思われ、グルーヴという名状しがたい何かが、確かにそこに存在しているのだということを感じさせる。
辺境のラッパーたち
立ち上がる「声の民族誌」
島村一平 / 青土社
¥3520((税込)
アメリカで生まれたヒップホップ文化。その中でも、リズミカルに韻を踏んだ言葉を繰り出すラップ音楽は世界中に広がり、その土地土地の言語や音楽と結びつき、様々な様相を呈している。戦火が絶えないガザやウクライナで、弾圧が続くチベットやイランで、格差にあえぐモンゴルやインドで、海の端の日本で、辺境の土地から発される叫びは、いわゆる朗々と歌い上げる歌唱とはまた違い、現代社会の歪みを鮮やかに映し出す。