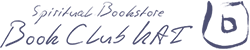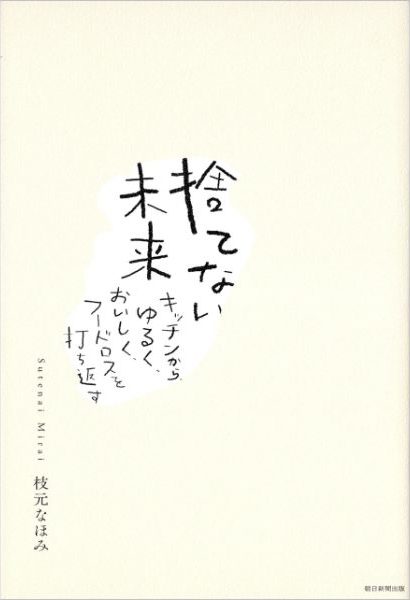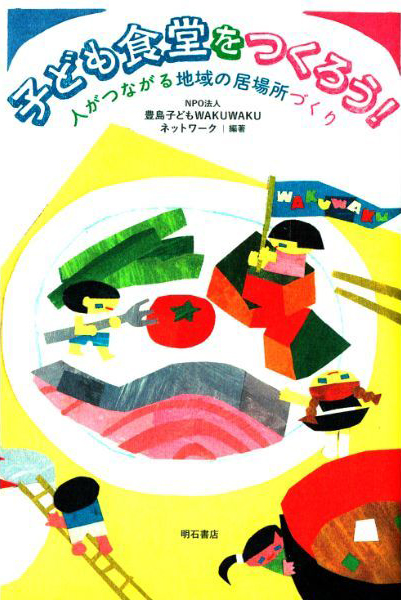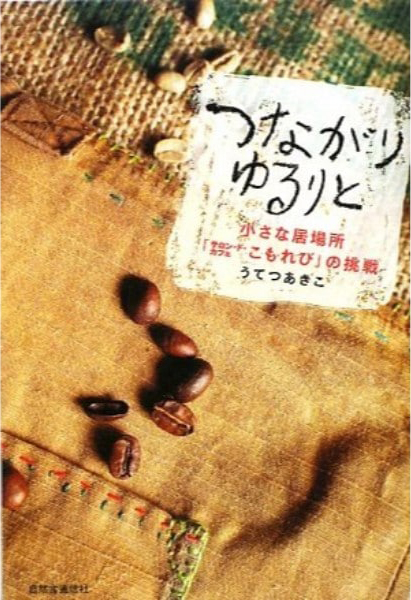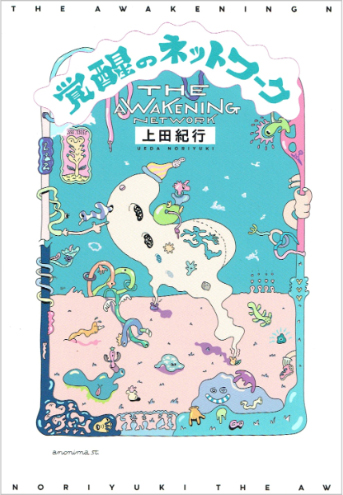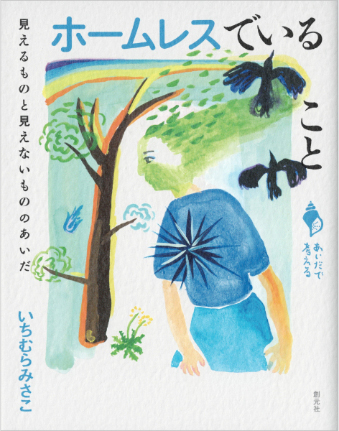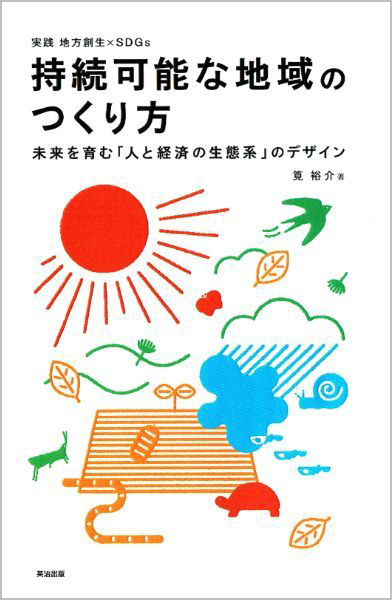「夜のパン屋さん」をご存じだろうか?
パン屋さんが営業時間内に売りつくすことができなかったパンを集め、
夜にまた別の場所で販売する試みだ。
夜でもパンが買え、フードロスをなくすばかりでなく、
そこには雇用の創出という意図が込められているという。
料理研究家で発案者の枝元なほみさん、スタッフの光枝萌美さんにお話をうかがううちに、
さらにもっと大きな可能性と希望が見えてきた――。
お手製のひんやりおいしい梅ソーダにシフォンケーキ。忙しい中、取材でおじゃましているにもかかわらず、なんともありがたいおもてなしをいただく。そしてあっ。テーブルの上に猫のキーちゃんがやってきた。
「紙が大好きなんです。テーブルの上に紙を見つけると目ざとく上がってきます。もう一匹、クーちゃんという子もいるんですよ」
枝元なほみさんのお話を聞きながら一緒にキーちゃんをなでさせてもらい、すっかりくつろいでしまう。いやいや、まったりしている場合じゃないぞ。「夜のパン屋さん」のお話をうかがわなくては。
自分は「ビッグイシュー・チルドレン」
「夜のパン屋さんは、2020年10月16日、〝世界食糧デー〟の日にスタートしました。2019年のWFP(国連世界食糧計画)のキャンペーンに私が携わったこともあって、始めるならこの日からにしようと決めていたんです」
枝元さんはこう切り出してくれた。「夜のパン屋さん」を理解してもらうために、すでにご存じの方も多いとは思うが、雑誌「THE BIG ISSUE」(以下、「ビッグイシュー」)について説明しよう。「ビッグイシュー」はホームレスや生活困窮者が正当に報酬を得て、社会復帰できる機会を提供する目的で1991年にイギリスで創刊された。日本版のスタートは2003年9月。街の路上でホームレスの方が雑誌を掲げ、販売している姿を見たことのある人も少なくないはずだ。隔週刊で、1冊あたり450円。このうち230円が販売者の収入になる。
枝元さんは「ビッグイシュー」の中に連載を持つほか、NPO法人ビッグイシュー基金共同代表も務めている。この「ビッグイシュー」の活動があって、「夜のパン屋さん」が実現可能になった。
「ビッグイシュー日本に、少しまとまった寄付をいただいたんです。それで、『雑誌を販売するだけでなく、なにかしらプロジェクトがやれたらいいね』なんて話していました。でも、大掛かりなプロジェクトなんて自分にはとても無理だと思い、なかなか具体的には踏み出せません。そんな時、いつもいろいろ教えてくれる北海道の知人によって、帯広にあるパン屋の満寿屋(ますや)さんの存在を知りました。満寿屋さんは北海道に7店舗あって、開店時間に残ったパンを本店に集めて、夜に販売してお客さんに喜ばれていたそうなんです。またかつては東京・自由が丘にも店舗があって、〈夜のパン屋さん〉にも参加してくださったんですよ。4代目の現在の社長さんは、別のお仕事で東京にいらした時も、ロスになってしまうパンたちに心いためて公園で配っていらしたと聞きました。
それを知ってピン! と来ましたね。『ビッグイシュー』の販売員さんは、東京だったらあちこちの街にいるし、雑誌の販売が終わる頃にパンをピックアップしてもらえばいいんじゃないか。これ、ちょっとしたアルバイトになるし、『ビッグイシュー』での利益にプラスアルファされるし、これはイケるぞ! と思ったんです」
枝元さんは自らを「ビッグイシュー・チルドレン」と呼ぶ。
「東京駅で寝ていたおじちゃんがいたんです。小さく折りたたんだ千円札を渡そうとしたら、『要らん!』。ピシャリと言われました。すごいショックです。私はその方のプライドも考えずに行動に出てしまったんですね。それから私は『ビッグイシュー』に関わる中でほんとうにたくさんのことを学びました」
では今では、もしそんな人を見かけた場合、どうしているのか? その回答がさすが料理研究家というか、独特でおもしろい。
「最近は駅でお見掛けすると、ダーッと走って駅弁を買い、『これ食べて!』と言うようにしています。こうすると、『おう、ありがとう』と言って食べてくれるんです(笑)」
そう、枝元さんは考えるだけでなく、常に自ら行動する人なのだ。
どう考えてもおかしい日本経済
行動する枝元さん。最初は名刺と「夜のパン屋さん」の企画書、「ビッグイシュー」、そして自身の著作を持って、飛び込みで一軒ずつあちこちのパン屋さんを回って歩いたというから驚く。
「ある程度そのお店でパンを買ってから、おずおずと『ちょっとお話よろしいでしょうか?』と切り出します。中には『テレビ見ました』『枝元さんですよね?』と言ってくださる方もいるけれど、だいたい『社長に聞いたら、ダメでした』という結果に。
飛び込みで行って最初にOKしてくれたのは東京・江戸川橋のナカノヤさん。ご主人が『うん、いいよ、やってあげる』と言ってくれた時のあの感じ、おそらく一生忘れないと思います」
ここで急いで書いておかなければいけないことがある。ここまで読んでくださった皆さんはおそらく、余ったパン、あとは捨てるばかりのパンを無料でもらいに行くのが「夜のパン屋さん」だと想像されるのではないだろうか。ところがこれが違うのだ。パンはあくまで購入するのである。1個ずつだと大変だからセットにしてもらい、値段を決めてもらったら、半額から60%の金額で卸してもらう。そして月末締めで支払いをする。
もともと捨てるしか行き場のないパンだから、利益ゼロのところが、こうして少しでも売れるわけだから、パン屋さんにとってデメリットはまったくないはずだ。ところがこんなことを一度もやったことのないパン屋さんにはピンと来ない。めんどくさい、という気持ちもきっとあるのだろう。
ここから枝元さんのお話は、「日本経済、ぜったいヘン」という話に発展(脱線?)していく。
「以前、あまり料理をしない番組で料理をした時のこと。アルバイト以下みたいなすごく安いギャラを言われました。他のことならともかく、私にとっては料理を提案することが仕事です。その金額では納得できません、と言いました。そうしたら次にお会いした時には倍の金額を提示されました。『言えばやってくれるのか』と思ったのもつかの間、『こちらの領収証に、〈交通費として〉と書いていただけますか?』と。
私、もうブチ切れて、その場で領収証を破り捨てました。日本経済、もう終わってるなと。
その点、『ビッグイシュー』は、『雑誌を作るのは会社だけど、売る人は個人商店です』と説明されました。雇う/雇われる、ではないフラットな関係。ああ、これはいいな、と思ったわけなんです」

破格のプレゼンで「夜パンB&Bカフェ」誕生
ここまで話をうかがった時、スタッフの光枝萌美さんが合流。話題は「夜のパン屋さん」の新展開である「夜パンB&Bカフェ」のことに移った。
「東京の練馬区にある築150年の古民家で、毎月1回、第2土曜日に開催しています。『夜のパン屋さん』が開く『昼間のカフェ』というわけです。ここで枝元さん監修の『エダモンカフェ』や『夜のパン屋さん』に参加のパン屋さんから届くおいしいパンの販売、穫れたて不揃い野菜マルシェ、そのほかキッズスペース、手芸スペースなどもあります。毎月テーマを設定して、例えば『LLブック』と言って、眼が見えないとか文字として認識できないとか、さまざまな障害のある人たちにもわかりやすく作られた本があるのですが、そうした読書文化のプロジェクトをやっている団体の方々を招いたりしました」
このカフェは、自動車メーカー「MINI」のスポンサードの下に行われているものだ。「B&B」とは、MINIがソーシャルアクションを応援する「BIG LOVE ACTION」と、「THE BIG ISSUE」の双方の頭文字から取ったもの。そしてこのMINIのサポートを獲得したのが、そう、またしても枝元さんのお点前。
「声をかけてもらってMINIのこのACTIONに参加し、56組の応募の中から絞り込まれた12組に残ることができました。さてそこから先は人生初のプレゼンテーションです。私は立て板に水のごとくスラスラしゃべるプレゼンが苦手だし、昔は転形劇場という劇団で芝居をやっていた人間でもあるので(枝元ファンの方には常識!)、ここは一つ、スティーブ・ジョブズみたいな言葉による説得力のあるプレゼンではなく、〈その場に存在する〉ことや、その場にいる人と〈しっかりつながる〉ことなどがやってみたかったのです。なので、出て行ってからしばらくの間は話さずに、ただ笑っていようと思いました。そしたら… なんとスポンサードしてもらえる3組の中に選ばれたんです(笑)」
プレゼンでの沈黙も、その言い返し方も、正直、理解不能だという気もする。しかし目の前で楽しそうに話す枝元さんを見ていると、「やるだろうな」としか思えない。
そしてそんな枝元さんもすごいが、MINIもまたすごい。
「3組に残った後、『何をどんなふうにやりたいのか』『何をサポートしてほしいのか』とZOOMで聞いてくれました。日本の企業のように、お金をあげてハイ終わり、じゃないんですね。私たちは、『夜パン』だと販売だけだから、もっと人と人がつながれるような場所を作りたいと、カフェを希望しました。するとMINIは毎月スタッフを派遣してくれて、MINI車のオーナーもボランティア参加。MINIグッズも無償提供し、売り上げはカフェの運営にあてていい、会場費も出してくれる、といった最上級のサポートをしてくれました。一緒にやろう、というその姿勢がほんとうにうれしいです」

閉店と開店のスイッチ 雨の中でも続々来客
枝元さん、光枝さんのお話をうかがった翌日、実際に「夜のパン屋さん」を訪れた。この日の販売場所は、東京・神楽坂にあるかもめブックス。書店の窓の外側に少し張り出した板張りの部分があり、そこに集めてきたパンを並べて販売する。
夜7時。かもめブックスの窓の前で、「夜のパン屋さん」が開店。かもめブックスは8時閉店だから、1時間だけ、本屋さんとパン屋さんが一緒に営業することになる(「夜のパン屋さん」は火・木・金曜が営業日だったが、2023年9月から月・木・金曜に変更)。
この日はあいにくの雨にもかかわらず、ほどなくどこからともなくお客さんが集まってくる。「おや、こんな時刻にこんな場所でパンを?」と興味深そうに寄って来る人もいるが、今日この場所この時刻にパンが買えることを知っていて来ている人のほうが多い印象である。
販売にはかつてホームレスだったり、なんらかのカタチで「ビッグイシュー」に関わってきた方たちと光枝さんがあたっている。少し会話を試みる。
「もう、この夜パンのお仕事は長いんですか?」
「特にパンに興味があったわけではないのですが、夜にパンを売るというアイデアに魅かれて参加して、どんどん面白くなって、気が付いたら3年経ってました」
「見ていると女性のお客様が多いですね」
「いつもだいたい8割が女性です」
「お客さんと会話して売るのは光枝さんで、皆さんはレジを?」
「いや、今日はたまたまそうなってますが、私たちもお客さんと話しながら販売します」
「屋外だと、真夏や真冬がキツくないですか?」
「夏は衛生管理の面でも心配な季節なので、お盆の頃などはしばらく休業しています。また冬はいちおう暖房もあるんですが、足の先なんて凍傷になったこともありました」
と、こんな感じ。
見ていると、「あ、今日はあの店のパンがある」とか、「前から一度来たいと思っていたんです」とか、多くのお客さんがなにかしら会話を交わしていく。枝元さんは「夜パンは販売だけだから、もっとつながりを」ということで、ネクストステージのカフェについて語ってくれた。確かにいま、目の前にあるのはまだ「つながり」ではないのかもしれない。でも、なんとなく想像していたよりも常連客が多いという事実は、そこが少しずつつながってきている、ということではないだろうか。
ここから聞こえる会話には「小さな芽」のような何かを感じる。ここに、ささやかな出会いがある。夜なのにパン屋さん、それもいろいろなお店のパンがセットで買えるという少し不思議な、ありそうで無かった試みの中に、いつもとは違う、あたらしい何かが、このコロナ禍の憂鬱な日本に、これから花咲くのかもしれない。

プロフィール
関連書籍紹介
捨てない未来
キッチンから、ゆるく、おいしく、フードロスを打ち返す
枝元なほみ / 朝日新聞出版
¥1980((税込)
2023年度の調査によれば、全国のこども食堂は前年度から1768箇所増え、9131箇所となった。貧困と所得格差が拡大しつづけるこの国で、「夜のパン屋さん」「大人食堂」などフードロスや貧困問題、農業生産者の支援活動に取り組む人気料理研究家が、未来を「捨てない」ためのオルタナティブな暮らしのアイデアを提案する。藤原辰史京都大准教授との対談、食材を活かしきる保存法、地球にやさしく美味しいレシピも豊富に紹介。
子ども食堂をつくろう!
人がつながる地域の居場所づくり
NPO法人豊島子どもWAKUWAKUネットワーク / 明石書店
¥1540(税込)
国や市区町村の制度を変えることは中々出来ないけれど、地域住民だからできることもある。本書は、子ども食堂の場所の決め方や、資金調達の方法、アレルギー対策など、子ども食堂を始めたい人に有用な情報を紹介。誰かがやってくれる社会から、自分たちでできることを始める社会へ!
つながりゆるりと
小さな居場所「サロン・ド・カフェ こもれび」の挑戦
うてつあきこ / 自然食通信社
¥1760((税込)
経済的貧困を抜け出ても、人間関係の貧困は人から生きる力を奪ってしまう。ホームレス支援団体「もやい」が営むカフェでは、コーヒー1杯100円で誰もが自由に交流できる場を提供し、そこに集う人生を結んでいく。人や社会とのつながりが生み出すパワーにふれる5年間の物語。
覚醒のネットワーク
THE AWAKENING NETWORK
上田紀行 / KTC中央出版
¥1650((税込)
たくさんの殻に囲まれた私たちの世界。社会にはびこる問題の根源を驚くほどやさしい言葉で解き明かしながら、一人ひとりが殻を破り、他者との間に開かれたネットワークを築いていくための道を提案する、1989年刊行の意識変革の名著、待望の復刊。文化人類学者であり、東京工業大学のリベラルアーツ研究教育院長である著者の原点となるこの本には、無力感や孤独感に苛まれた人々の心に勇気と活力の火を灯す、熱いエネルギーがほとばしっている。
シリーズ「あいだで考える」
ホームレスでいること
見えるものと見えないもののあいだ
いちむらみさこ / 創元社
¥1540((税込)
駅周辺や公園で身を横たえている人たちを見かけた時、私たちがつい心の感度を下げ、目を背けてしまいがちになるのは、彼らの姿に貧困や孤独を感じ、明日の自分の姿を見ているような、漠然とした不安を掻き立てられるからだろうか。行政はホームレスを救済すべき存在として「保護」し、「社会復帰」させようとするが、それは本当に本人たちの望むところなのか。著者は公園のテントに20年以上暮らし、仲間と共に生きる場をつくりながら、様々な社会活動を行ってきた。所有するとはどういうことか。 家のある人もない人も、私たちが私たちのままでいるためにはどうすれば良いのか? 静かに問いかけてくる。
持続可能な地域の作り方
未来を育む「人と経済の生態系」のデザイン
筧裕介 / 英治出版
¥2640((税込)
SDGsの魅力は「誰一人取り残さない社会は“皆でつくることから生まれる”」という命題にあるのかもしれない。様々な思いを持った人たちが集い、ともに未来を作るとは。その心構えや方法を、地域社会デザインの実務家である著者がやさしく指し示した実践本。最終章「貨幣経済に依存しない豊かさ」も示唆にあふれる。