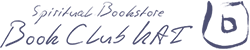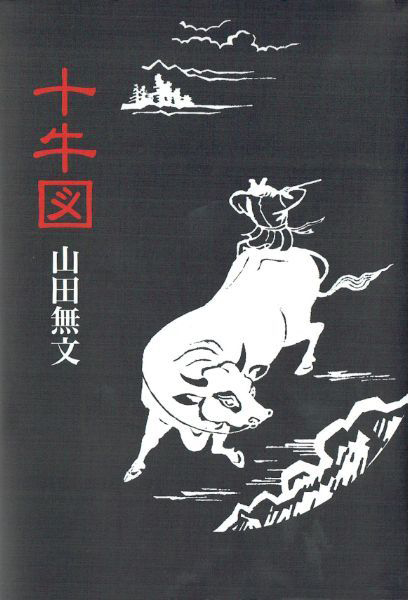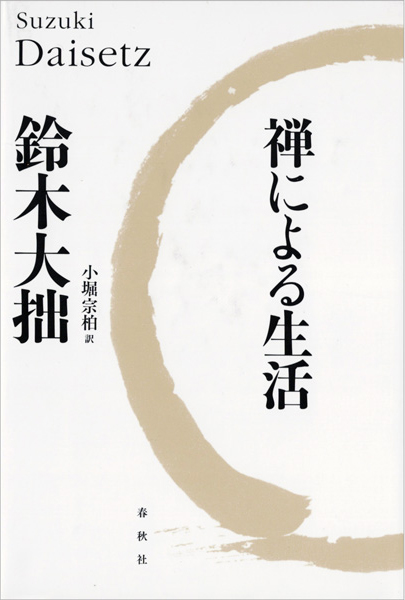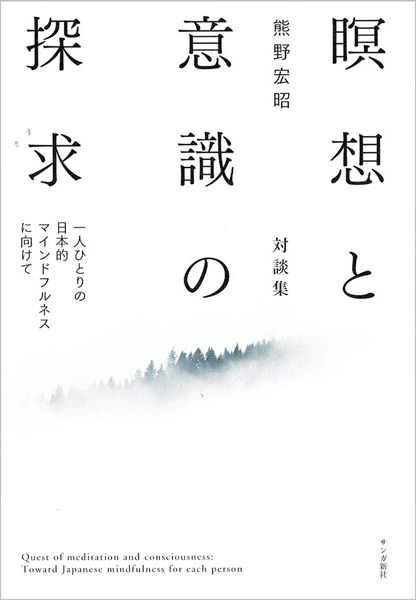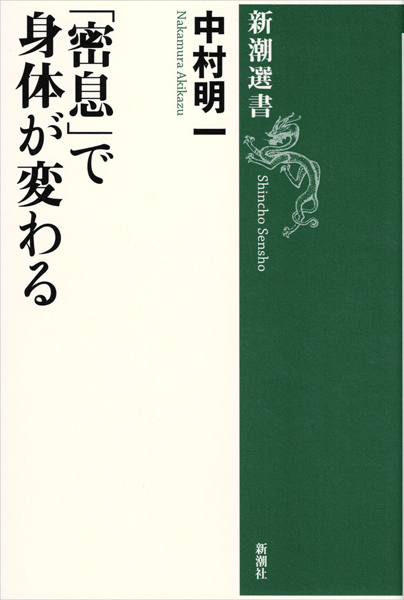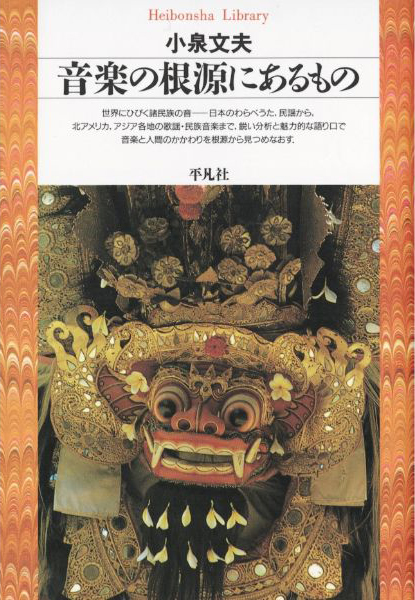尺八という楽器はその源流において「禅」と深い繋がりがあることをご存知だろうか。
江戸時代、尺八は禅の宗派普化宗の虚無僧(こむそう)のみが持つことを許され、その曲は古典本曲として全国の禅寺に口伝で受け継がれてきたという。禅僧たちが悟りを開くために尺八を吹きながらする修行を「吹禅(すいぜん)」と呼び、それを実践し探究されているのが工藤煉山(れんざん)さんだ。彼は虚無僧が吹いていたとされている “地無し尺八”を竹林で竹を採るところから始めて製作している。また、演奏活動のほかに、禅とマインドフルネスの国際カンファレンス“Zen 2.0”に度々登壇し、尺八と禅とも深い繋がりのある「呼吸法」についてのワークショップも行い、禅の視点から見た環境問題について話をする機会もあるという。尺八の原点を突き詰めていきながら、“禅”と出会い、“呼吸法”を探求し、それが環境問題にも繋がってゆく。その知見は今の時代に生きるヒントのようなものがある気がして、彼が「坐禅と吹禅」という会を定期的に開いている「東光庵」(箱根芦之湯)でお話を伺った。

小学5年生で出会い やがて病と苦闘の日々
小学校5年生の時に押入れ探索をしていて尺八が出てきたことから興味を持った工藤さん。なかなか音を出すことができず、学校以外の時間はずっと尺八を吹いていたという。
「それで、“ぽっ”と音が鳴ったのがすごく達成感があって続けてしまった、というのがいつもお話ししていることなんですが、実はもう一つあって、その当時転校したんです。転校した時にすごく寂しかったんですよね。そういうことも重なって尺八にのめり込むようになったんです。尺八には都山流と琴古流という二大流派があるのですが、僕が住んでいた札幌で盛んだった都山流の門を小学校6年の時に叩きました」
中学に入ると一度尺八をやめて坂本龍一や小室哲哉の音楽を好んで聴いていたそうだが、高校時代に自分の進路について真剣に考えた時に、将来は尺八や音楽をやっていきたいと決意し、憧れの坂本龍一の母校である東京芸大に入学。大学院まで進んだ。
― 卒業後はどうされたんですか?
「今の邦楽の世界はとても上下関係が厳しいですし、すごく狭いんです。世界や世間を知らないで、音楽と言えるんだろうかという思いがすごく強くなっていって、ロンドンに1年行き、自分の実力とか音楽へのパッションがどれだけのものか知りたくて、向こうで“Busking”と呼ばれる路上の演奏を始めました。ただ、続けていく中で、やはり日本から発信したり実績を上げないといけないと感じたので、日本に戻ることにしました」
― 帰国してからは?
「いろんなところで演奏しました。その中にセレブの方が使っている老人ホームを回る仕事もあったんですが、お金回りが良くて、お金を稼ぐって簡単だなって思っちゃったんです(笑)。それに童謡や『荒城の月』とか『紅葉(もみじ)』とか、有名な曲を演奏するとみなさん感動してくれて。そこでまた、音楽で人を感動させるなんて簡単だと思っちゃったんですよね(笑)。恥ずかしい限りですが。
実はその後、耳がメニエール病になってしまって仕事ができなくなってしまいました。それで音楽はやめざるを得なくて、韓国で日本語教師を1年くらいやりました。当時韓国語も勉強していたんです。ただ仕事の時間が不規則で睡眠不足になって耳もなかなか回復しないのでまた日本に戻りました。
帰ってきてから今度は鬱病になったんです。両親との関係やいろんなことが原因で。それでまた働けなくなってしまったんです、1年くらいですかね。それでも働かなきゃと思ってリサイクルをやっている会社に就職しました」
「自分がない音」で 民族音楽に帰したい
― 尺八奏者としての活動を再開したきっかけは何だったんですか?
「間違いなく3.11ですね。芸大の知り合いとチャリティコンサートをやったんです。その時に、音楽の力ってすごいな、あらためて音楽っていいなと思えました。それと、社会的な貢献をしながら音楽ができないかという風に考え始めて活動を再開しました」
― 工藤さんは禅と深く関わって活動をされていますが、どうして興味を持たれたんですか?
「それがいまだによく分からないんですが、もともと小さい頃から命について考えていました。禅という言葉を知って共感し始めたのは三十代半ばからだったと思います。それから鎌倉に住むようになってさらに興味を持って、実際に寺に行き坐禅を学んだりしました。尺八はもともと禅宗の一派の普化宗で吹かれる楽器だったのでそういう興味もありました。ただ、都山流は現代曲が得意な奏者が多かったので、都山流を背負っていると思っちゃうと表立ってやりづらいというのはありましたね。でも基本からやらないと禅と言えないんじゃないかと思っていたところ、ご縁で吹禅をやっている師匠の方と出会えて、そこで学ばせていただきました」
― 吹禅とそれまで学んできた尺八とでは吹き方に違いはあるのでしょうか?
「呼吸法や演奏は一緒だと思います。ですが、音色やそれに求める哲学性は違うと思います。例えば都山流とか、今の演奏家はテクニックを求めているわけですよね。音を“遠く”に届けるんです。でも、僕が最終的に求めているのは、小さな、本当に“自分がない音”で吹禅をやりたいという思いで今に至っています。そういう意味では真逆の方向ですね。普通の尺八がどんどん西洋的になってきているのに対して、僕は民族音楽的にしたいと思っています。伝統音楽ではなくて、民族音楽に帰したいという思いで吹禅をしている感じですね」
― 本来あったかたちにしたいということですか?
「本来あったかたち、というのもそうですが、それよりもっと深掘りしたいですね。
坐禅をしていて、本当に何も考えられない、自分が「ただある」という状態になれるように、吹禅でも全く同じ状態になることがあるんです。そこに何かある、とも、ない、とも言えないんですが、そこを知りたいと思っています」
吹禅を教えてくれた方が竹を取って尺八を作っていたことで、ご自身でも竹取りを始めるようになったという工藤さん。今、尺八用の竹を取る竹林は群馬にあるそうだ。
「整備されていない竹林って本当に怖いんですよね。何気なく歩いていると、ピカーンと光っているような、生命力が宿ったみたいな竹があるんですよね。見た瞬間に分かります。その竹を取ろうとすると、なんだか嫌な気分になるんです。命を取っているという感じがして。そのまわりも根っこでつながっている兄弟、家族なので、みんなもザワザワザワザワってする、そういう恐怖感がしみついています。だから、乱獲はしないようにと僕は思っていますし、お弟子たちにも伝えています」
― 吹禅の尺八と普通の尺八は違うんですか?
「今の尺八は中に漆が使われているんですが、吹禅で使う地無し尺八はそのままくりぬいただけなんです。なので、より自然に近いですし、次の生命のあり方のためにあなたの命を使わせてくださいという気持ちが音にもなるような気がするんです。竹は二十年もすれば枯れてしまいますが、尺八にすることで命を生かすという感じでしょうか。尺八は三年の竹を取るんですけど、整備しながら少しずつ取らせていただくということが重要かなと思います」



メッセージにリアクションが! 坂本龍一氏とコラボ
― 2020年に坂本龍一さんと「series─incomplete“時光 Jiko”」という作品をコラボされていますが、どういう経緯で知り合われたんですか?
「尺八をやめていた頃なんですが、坂本さんのTwitterを見ていたら、ライブのピアノの音が同じ日なのにちょっと違っていたんです。それで、そのとき酔っ払っていたので(笑)勢いで『教授、ピアノの音色と調律って前半と後半で変えていますか?』とメッセージを送ったらリアクションがあったんです。そして、しばらくしたら、彼からFacebookにリクエストとメッセージが来たんですよ。『えっご本人ですか?』と返したら『フフフ』って返信が来ました(笑)。
それから十年くらい経って、知り合いの音楽家が坂本さんとセッションすることになったので、会わせてほしいとお願いして、現場で初めてお話ししました。環境問題のこととか、吹禅のこととか。それで、『工藤君、なんか音源送ってみない?』って言われて、送ったらコラボという形になったんです。それ以来、時々メールなどでやりとりさせていただくようになって。坂本さんが亡くなる数ヶ月前に僕が作っている“空道(くうどう)”という2mくらいの尺八に関してもアドバイスくださったんです。ですから“空道”も世界に広めたいなあという思いでやっています」
― 今後はどのような活動をしていきたいですか?
坐禅をしたり吹禅をする反面、普通の演奏家として社会に接すると、痛感するのはやはり知名度だったり、影響力だったりに負けている自分、というか、音楽は勝ち負けではないですけど、心を蔑ろにされることがけっこうあるんですよね。環境問題についても話す機会もあるのですが、知名度がないと誰も聞いてくれないというのも感じていて。そういうこととずっと葛藤しながらやっていくんだろうな、とは思っています。
でも、やはり山から下りて社会に身を置いてそれを体現することこそが、禅のあり方だと僕は思っています。うまくいくこともあれば、道に迷ったりすることもあって、それがまた禅なんだろうと。ただ、どんな時も自分は“心ありき”でいるということだけは守っていきたいと思っています」

プロフィール
工藤煉山(くどう れんざん)
尺八演奏家。尺八道場「虚道」主宰。 尺八本来の演奏である吹禅(江戸時代に普化宗の 禅僧が演奏した古典本曲)をライフワークとし、禅の街、鎌倉から尺八を広めている。また、ヨガ、ロルフィング、アレキサンダーテクニーク、中国気功などを習得。演奏法だけでなく、身体性や呼吸法、禅の哲学から心のあり方などを伝えている。
最近の主な活動
■ Zen2.0(禅の国際カンファレンス)2017年、2018年、2021年~2024年登壇
■ 清水寺 Film exhibition 「KIYOMIZU – Cycle of blessings」(https://feel.kiyomizudera.or.jp/project/1223)オープニングとクロージング曲で参加(2024年)
■ 坂本龍一 「series – incomplete “時光 Jiko”」でコラボレーション(2020年)
■ 新宿御苑 「菊花壇展ライトアップ」演奏&演奏時の演出担当(2019年)
関連書籍紹介
十牛図
禅の悟りにいたる十のプロセス
山田無文 / 公益財団法人 禅文化研究所 / 2200円(税込)
真の自己を牛にたとえ、悟りを求める人の過程を10枚の絵に託して表現してみせた十牛図。よく禅で、象徴的に利用される、「○」の一文字。その後に、まだ二つもプロセスが残っているのが禅の奥深いところだろう。禅の奥深さを、一切の言葉を使わずに表現する。
鈴木大拙 / 春秋社 / 2420円(税込)
本書は1950年英語で出版された鈴木大拙による『Living by Zen』の完全邦訳版。これまでの著作で述べてこなかった〈禅の意識〉について説明する。本当に禅が人間の生活の中に生きるためにはどうすればよいのか。概念、悟り、悟りへの道、公案、禅による生活をそれぞれにとき、禅とともに生きるという意味を明らかにする。
瞑想と意識の探求
一人ひとりの日本的マインドフルネスに向けて
熊野宏昭 / サンガ新社 / 3960円(税込)
瞑想を実践する中で現れてくる、ただ気づきだけがある無心の状態。無心の状態でできることとは? そして無心のその先は? マインドフルネスを診療に取り入れる心療内科医が、様々な疑問について僧侶や宗教学者、気鋭の数学者らと語り合う。集中瞑想のみを修行してきた禅の僧侶が、観察瞑想を行ったら? 自力では話せない知的障害や肢体不自由を持つ人々との驚くべきコミュニケーションの様子など、人の意識を巡る対話集。
中村明一 / 新潮社 / 1650円(税込)
武術、禅、茶の湯、日本文化の原点は、畳に座り、帯を腰に締めて着物を身につけて自然に行う呼吸法「密息」にあるという。日本人の身体に眠っている呼吸をすれば、心が落ちつき、感覚が鋭敏になってくる。「息の技術」を演奏家の著者が伝授してくれる。
小泉文夫 / 平凡社 / 1760円(税込)
世界にひびく諸民族の音-日本のわらべうた、民謡から、北アメリカ、アジア各地の歌謡・民族音楽まで、鋭い分析と魅力的な語り口で音楽と人間のかかわりを根源から見つめなおす。 ―出版社紹介より