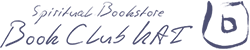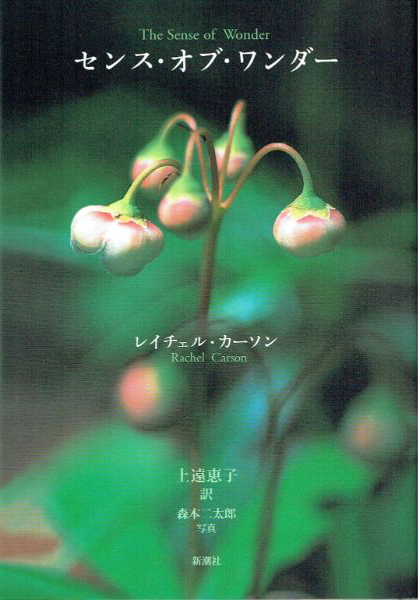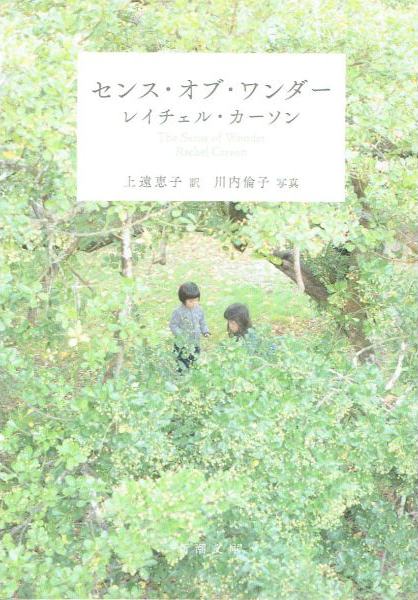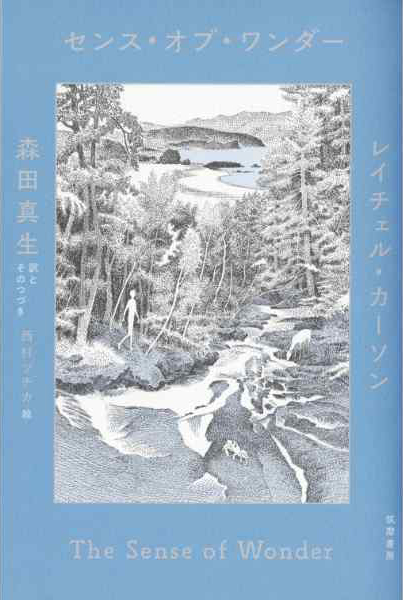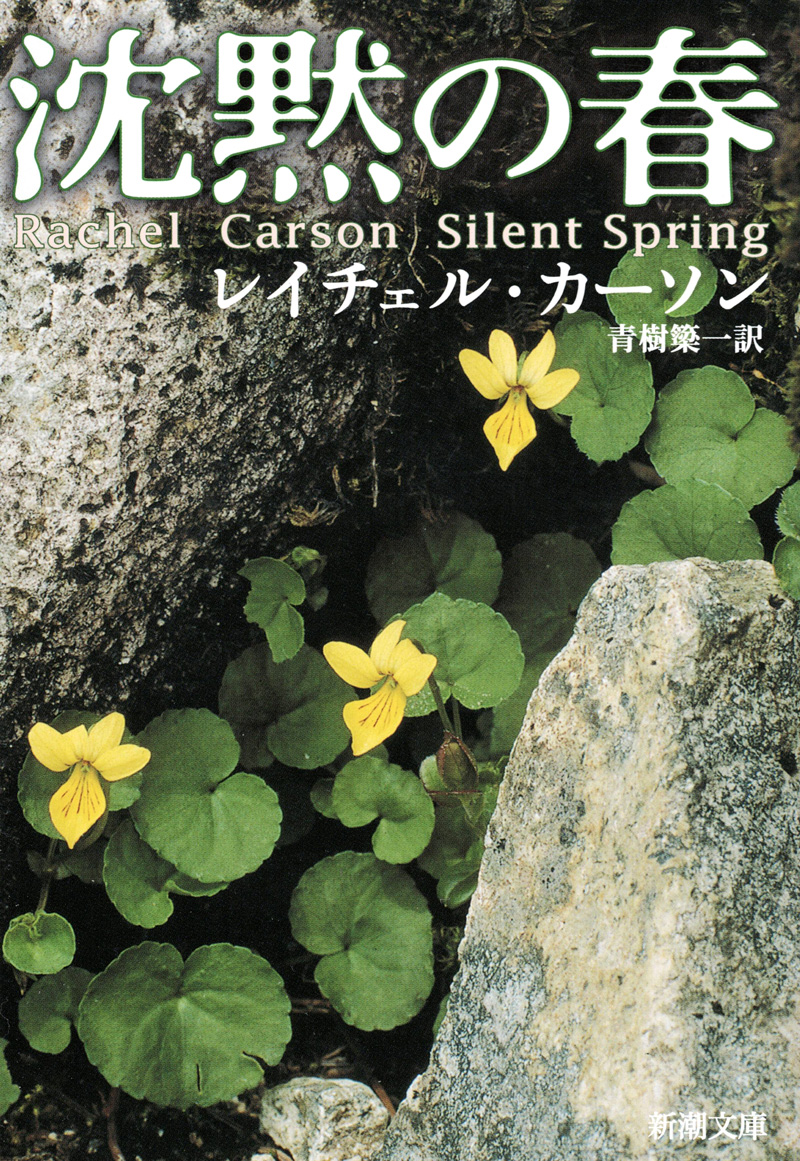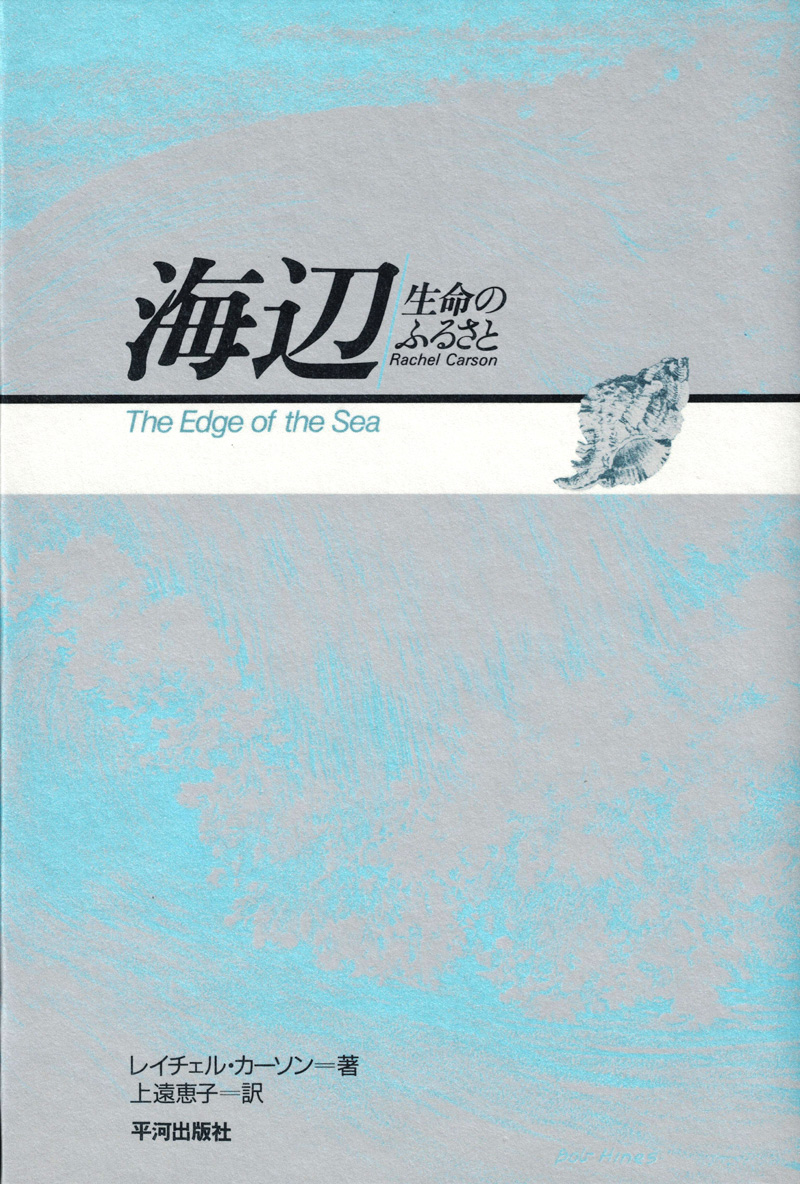レイチェル・カーソンといえば、DDTの危険性をいち早く告発した世界的ベストセラー『沈黙の春』の著者として知られる。
その思想を継承し、環境教育や読書会、セミナー、自然観察体験などを実践する協会が日本に存在する。
レイチェル・カーソン日本協会会長の上遠恵子さんにお話をうかがった。
きっかけは父の勧め
1907年、アメリカはペンシルベニア州スプリングデールで生まれたレイチェル・カーソン。ジョンズ・ホプキンス大学で修士号を得たのち、漁業局で政府刊行物の編集などの公務をこなしながら、大西洋岸に生きる海の生物たちの生態を克明に記したデビュー作『潮風の下で』(上遠恵子訳、ヤマケイ文庫)で 自然の語り部としての一歩を踏み出す。その後、『われらをめぐる海』(日下実男訳、ハヤカワ文庫)、『海辺』(上遠恵子訳、平凡社ライブラリー)を出版し、海の三部作の著者として親しまれた。そして62年に発表された『沈黙の春』は、環境破壊に警告を発した先駆的な書物として世界中で読まれ、一躍、彼女の名は広く知られるようになった。
「今から60年以上も前に、自然破壊に対する告発の本を世に問うというのはたいへんな先見の明だと思います。以来、ずっと読み継がれ、100刷以上のロングセラーになっています。私が父から勧められて読んだ時には彼女はすでに亡くなっていて、残念ながらお目にかかったことはないんですね」
レイチェル・カーソン日本協会会長で、カーソンの本を何冊も訳出している上遠恵子さんはこう語る。レイチェル・カーソンは『沈黙の春』を出したわずか2年後、64年に56歳で亡くなっているから、直接対面できなかったのも無理はない。しかし上遠さんが『沈黙の春』を読んだのは日本人としては最初期の部類に入るはずだし(なにしろまだ日本語訳が出ていない)、その出会いの傍らには、公務員であると同時に昆虫学者でもあったお父様の存在があるようだ。
「父は農林省にいたので、農薬のマイナス面を書いてアメリカで大きな話題になっていた『沈黙の春』のことは当然知っていて、原書で『これを読め』と渡されました」
ところが上遠さんは当初、『沈黙の春』を素直に受け入れることはできなかったという。
「私が小学6年生の時に太平洋戦争が始まりました。英語の授業なんてどんどん減って、工場に勤労動員されます。そして食糧難。みんな腹ペコです。害虫もたくさんいました。敗戦後にアメリカからDDT(有機塩素系殺虫剤)が入ってきて、農薬として使われたばかりでなく家庭用にもたくさん使われ、ノミやシラミ退治によく効きました。駅などでは、保健所の人に頭からDDTの粉を吹きかけられたものです。そういう記憶があるから、食料もちゃんとあって、余裕のあるアメリカの人からDDTが危険だって言われても、なかなか受け入れられませんでした」
そんな上遠さんが自身の思いを反省し、しっかり勉強しようと考えたきっかけとして、一人の女性ジャーナリストの存在があった。
「朝日新聞記者でフェミニストとしても著名な松井やよりさん(故人)が、厚生省担当の時に、母乳からDDTが検出されたとスクープしたんですね。それを読んで、腹ペコだった、食糧難の時に助かったなんて言ってられない、真剣に学ばなくてはと痛感しました」
ここで、同席していた関東フォーラムの小川真理子さんが解説をしてくれる。
「スクープの中にはDDTのほかBHCもあって、これらは脂溶性なんです。水ではなく油に溶ける。そして、特にお乳に出てしまう」
その母乳を飲むのは未来ある赤ちゃんである。それを知らないあいだにお母さんが飲ませてしまったら……事の重大さがこれだけで理解できる。
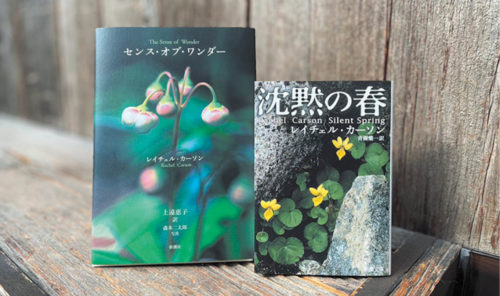
1988年5月27日 レイチェル・カーソン日本 協会設立
『沈黙の春』刊行から四半世紀。1987年に、全大阪消費者団体連絡会事務局長・下垣内博氏の発案を基礎として「レイチェル・カーソン生誕80年記念事業」が行われ、カーソンの警告と思想を現実の環境と照らし合わせ、日本で啓蒙活動を広げていこうという機運が生まれる。その背景には、当時高まりつつあった公害問題への関心などもあるようだ。20代から80代まで年齢層もバラバラ、研究者に弁護士、栄養士、ジャーナリスト、消費者・市民運動のリーダー、主婦などが準備委員となり、メインイベントの記念集会では300名以上の参加者があったという。この盛り上がりを受けて、翌88年5月27日、カーソンの誕生日にレイチェル・カーソン日本協会が設立された。
「87年の動きを毎日新聞の記事で知った私は、新聞社の知人に頼んで主催者の方と連絡を取りました。集会場では『これ1回限りではなく、人類の恩人であるカーソンに学び、持続的に検証していこう』という声が出てきて、それが協会発足の流れになったようです。ですから、ある時期から私が理事長ということになりましたが、始めたのは大阪の方々で、私は完全に後発、混ぜていただいた人間です」
大阪を中心に毎年開かれていたシンポジウムや勉強会は、だんだん人数も増え、関西フォーラム、関東フォーラム、北海道の会、東海フォーラムなどと分科会的に発展していく。
関東では、月に1回、自然を語る会(あるいは読書会)が行われ、2024年はまさに『沈黙の春』を皆で読み、語り合っているという。また毎年一度は日比谷図書文化館コンベンションホールで講演会が開かれ、これまで生命誌研究者の中村桂子さん、エッセイストでNPO法人「森は海の恋人」代表の畠山重篤さん、生物学者の福岡伸一さんら錚々たる面々が講演をしている。

あの牧野富太郎と交流!
お話をうかがうなかで、思わず「えっ、すごい!」と声が出てしまう逸話があった。上遠さんは少女時代、あの牧野富太郎と何度も対話しているのだ。
「東大の理学部出身の父が牧野さんと面識があり、父に連れられて何度か牧野さんの植物同好会に行きました。小学生の頃です。当時牧野さんは70代前半だったと思いますが、ほんとうにおだやかでやさしい、いつもニコニコしているおじいちゃんでした。キク科の多年草植物で、大きな葉っぱに切れ込みがあることからヤブレガサという植物があるのですが、小雨が降っていたある時、『これじゃ傘にならないね』なんて語りかけてくれたのを憶えています」
なんとステキな思い出だろう。牧野富太郎という植物学の巨人が語りかけた少女は、のちにレイチェル・カーソンという、地球環境を考える際、日本協会の方が言うように「人類の恩人」とも言うべきもうひとりの巨人を顕彰する仕事につく女性だったのだ。上遠恵子さんをつなぎ役として牧野富太郎とレイチェル・カーソンという2人の「恩人」が出会うような、そんなスケールの大きな光景を想像してしまうではないか。
そして牧野博士が少女の上遠さんに語りかけたように、レイチェル・カーソンの遺作『センス・オブ・ワンダー』にはロジャーという少年が重要な話し相手として登場する。生涯独身だったレイチェル・カーソンに子どもは無かったが、姪の息子のロジャーを養子にして、2人で自然の中を探索しながら語り合い、ロジャーはみずみずしい感受性を伸ばしていった。
「かわいらしかったロジャーはその後、成人してからは大男になって、パソコンや音楽関係の仕事をしてましたけどね(笑)。『センス・オブ・ワンダー』を映画化した『センス・オブ・ワンダー レイチェル・カーソンの贈りもの』(グループ現代制作)という作品があるんですが、ここにはロジャーの息子のイアン君が森の中を走り回るシーンがあります」
小川さんがここでこの映画について語ってくださる。
「次々に展開があるような映画ではないんですが、レイチェルのメイン州の別荘付近のうつくしい自然の中で上遠さんが朗読なさっていて、これがとてもヒーリングな感じですばらしいんです」
「『センス・オブ・ワンダー』はそれこそ詩のような本ですね。彼女は文学者を志していたわけだから、それもうなずけます」と、これも小川さん。
そうなのだ。文学者志向だった彼女は同時に幼い頃から自然と生き物が大好きな少女でもあり、この彼女の中の文学と生物学を融合させたのが「書く」という行為だった。
再び上遠さんが解説してくれる。
「ある時、7分間のラジオ番組で台本を書くアルバイトがあったんです。その際、レイチェルは7分間の魚の物語を作り、これがとても評判が良かったんですね。彼女は科学的に正確に、しかも一般の人たちがワクワクするような文章を書くことができたのです」
自分次第でどこでも「センス・オブ・ワンダー」は稼働する
レイチェル・カーソンの最後の本、『センス・オブ・ワンダー』は、読者にすぐ隣から静かな声で語りかけてくれるような、繊細でうつくしい書物だ。そしておそらく、誰が読んでもこの本の中で語られているメインのメッセージを受け取り間違う人はいないだろう。私たちを取り巻く自然とは、「知る」ことよりも「感じる」ことがまず大切、というメッセージだ。
「感じることが第一、というのは間違いなくあの本の最大のメッセージです。でも、自然の中でとにかく感じて、感じればもうそれだけでいいのだということではなくて、不思議だな、どうしてかな、と発展していくことが素晴らしいのです」(上遠さん)
「感じることが、次に知ることにつながっていく。その時、知識を詰め込むような、やらされる勉強ではなくて、まず感じて、好きになって、『これはいったいなんだろう?』と心から興味を持って学ぶことが、いちばん大事なんですね」(小川さん)
忙しくて……とか、仕事が……とすぐ口にして、自然体験は夏休みのような特別な時に……なんて思いがちの私たち。しかし自然はそんなふうに、距離的にも気持ちの上でも、はるか遠くにあるものなんだろうか。
「それこそマンションのベランダの鉢一つでも自然を感じられるはずで、自分次第でどこにいても『センス・オブ・ワンダー』は働きます。大自然の中に行かなきゃ、なんて思うのはむしろイメージでしかない。最近は皆さん、電車に乗ってもスマホばかり見ていますね。下ばかり見ている。それよりも車窓から外を見て、『今日の空、きれいだな』と感じることのほうがどれだけ豊かなことか。そういう小さなこと、ささやかな日常こそ、大切なものだと思います」
御年95歳、長い時間、レイチェル・カーソンの言葉、その思想と共に生きた上遠恵子さんのこの自然さ、そのお隣で初対面のわれわれと上遠さんのやりとりを見つめながら静かに微笑み、遠慮がちに会話に加わってくれる小川真理子さんの微笑み。
ふだんは忘れがちなその確かな温度を感じた得難い取材経験だった。

プロフィール
レイチェル・カーソン日本協会
環境問題の古典『沈黙の春』で地球の悲鳴を伝え、『センス・オブ・ワンダー』で幼児期からの自然との関わりの大切さを説いた海洋生物学者・作家のレイチェル・カーソンの生涯や思想を、環境教育・読書会・勉強会・セミナー・自然観察/体験などの諸活動を通じて広く社会に発信し、かけがえのない自然や環境を保全することを目的とした団体として日本各地で活動中。
関連書籍紹介
レイチェル・カーソン 著、上遠恵子 訳 / 新潮社
1650円(税込)
早くから環境問題に取り組み、現代文明に警鐘を鳴らしてきた著者が、すべての人が生まれながらに持つ「センス・オブ・ワンダー」、つまり「神秘さや不思議さに目を見はる感性」を、いつまでも失わないでほしいという願いを込めた本書。嵐の夜の海の荒々しい興奮、夏の森の散歩で出会う岩やシダ…。生きることの喜びを思い出させてくれる。
レイチェル・カーソン 著、上遠恵子 訳 / 新潮社
737円(税込)
レイチェル・カーソンによる、自然の神秘、不思議に対する、尽きない好奇心と瑞々しい感性にあふれた世界的ベストセラーを、川内倫子の美しい写真、そして新たに寄稿された、福岡伸一、若松英輔、大隅典子、角野栄子の解説エッセイとともに贈る。
センス・オブ・ワンダー
レイチェル・カーソン 著、森田真生 著・訳 / 筑摩書房
1980円(税込)
『数学する身体』『数学の贈り物』などの著作で知られる独立研究者、森田真生による世界的ベストセラー『センス・オブ・ワンダー』の新訳。未完の作品でもある本書の続きとして訳者が執筆した、「僕たちの『センス・オブ・ワンダー』」を加えた本書は、著者カーソンと70年後の現代を生きる訳者との呼応を形にした構成となっている。
レイチェル・カーソン 著、青樹簗一 訳 / 新潮社
825円(税込)
生命が目覚める春なのに命の営みが聞こえてこない。実際に起こりうるこの「沈黙した春」を著者は危惧する。殺虫剤の過剰な使用が、生態系を狂わせ、食物連鎖を死に変える。環境問題に早くから警鐘をならしてきた著者の考える解決策とは? 輝き続ける名著。
レイチェル・カーソン 著、上遠恵子 訳 / 平河出版社
2530円(税込)
潮の満ち引きによって、海にもなり陸にもなる海辺では、長い年月をかけて、劇的な生命の進化のドラマが演じられた。そこで繰り広げられる生命力溢れる生物たちの神秘の世界を紹介する。化学物質がもたらす環境汚染について警鐘をならした『沈黙の春』の著者の原点ともいえる書だ。