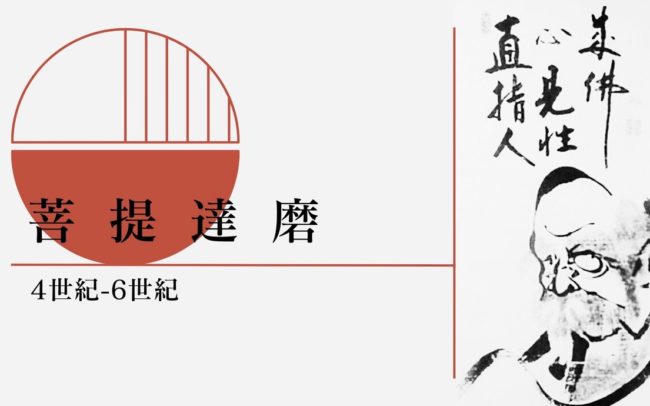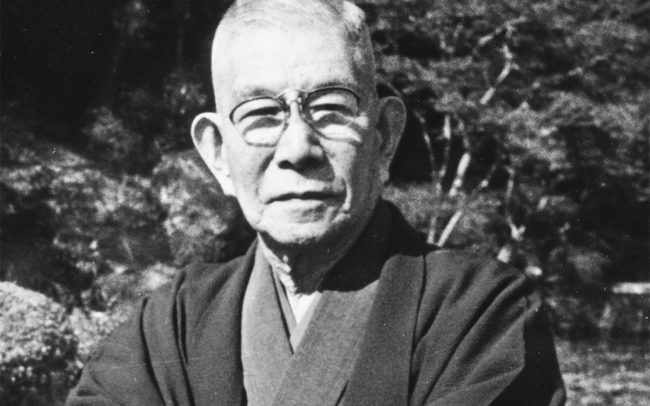Meeting With Remarkable People #77
菩提達磨
4世紀-6世紀
日本人にとって、「だるまさん」は親しい存在。
何度倒しても起きあがる「七転び八起き」、
願い事がかなったら目に墨を入れるなど、
赤い張子のだるまは人生を応援する縁起物として、
今も日本人の中で生き続けています。
しかし、実在した達磨は、
すさまじい修行の末に悟りの境地に達した、激烈な僧でした。
世界に禅というひとつの潮流を生み出した、達磨とはいかなる存在だったのでしょうか。
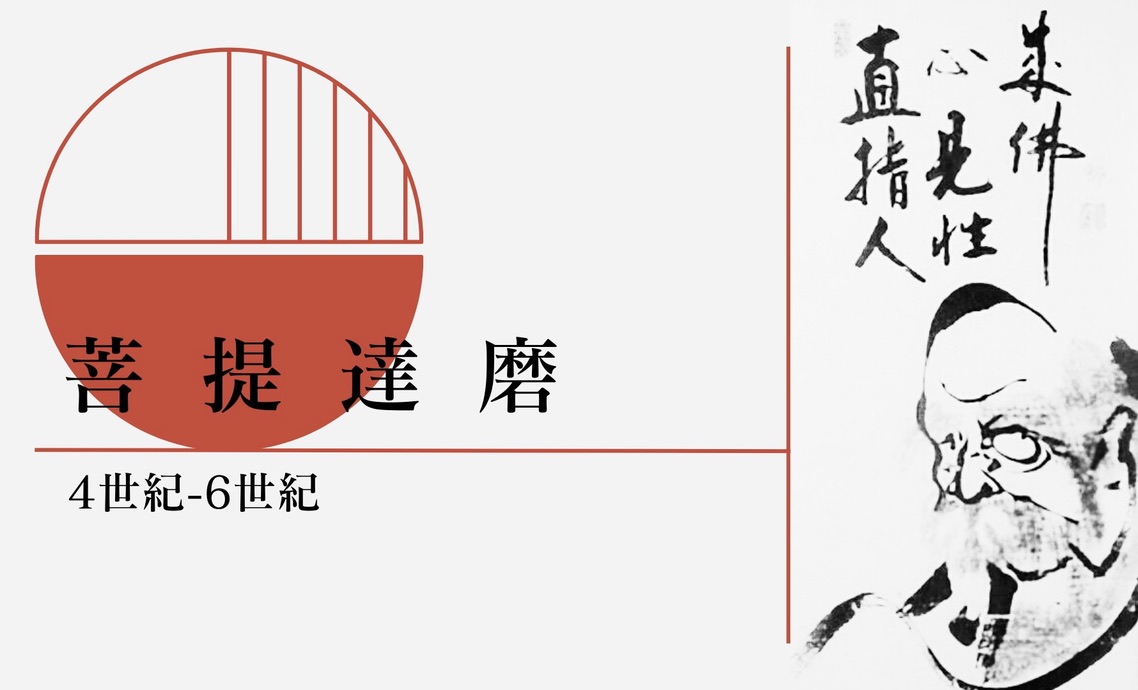
伝説の人物の常として、達磨の出生には不明な部分が多い。広く知られている説は、南インド、香至王国の第三王子であったということだ。仏教に帰依するきっかけについて、伝説はこう伝えている。ある日、釈迦の仏法を継いだ27代目の祖師、般若多羅(はんにゃたら)が王宮にやってきたので、王はすばらしい宝珠を与えた。般若多羅は王子たちに「この宝珠にまさるものはあるか? 」と問うと、他の王子は「ない」と答えたが、ただひとり達磨だけは、「物である宝珠より、仏陀の知恵の方が価値がある」と答えたという。それを聞いた般若多羅は、達磨を弟子として受け入れ、後に第28代目の祖として「菩提達磨(ボーディダルマ)」という名を授けた。「ダルマ」とは、サンスクリット語で「法」を表すもの。それから60歳頃まで、彼はインドで仏教の布教に努めたという。
師の死後、達磨は中国に渡ることを決意する。達磨がなぜ東を目指したのかは、後に禅の公案になっている。しかし、本当のところは謎に包まれたままだ。達磨の教えを後に弟子がまとめた『二入四行論(ににゅうしぎょうろん)』によれば、西暦520年頃、彼は、航海に3年の月日を費やして広州に上陸した。当時の中国は南北朝に分かれていて、達磨がまず謁見したのは、南朝の梁を治める武帝だった。武帝は以前から仏教を信仰しており、天竺から来た高僧を喜んで迎えたという。禅の公案に、武帝と達磨の問答がある。武帝は「私は今までたくさん寺を造り僧を育てて来た。これはどのくらいの功徳になっているだろうか」と聞いた。それに対して、達磨は「功徳は何も無い」と答えた。「では仏教における聖なる真理は何か」と聞くと「空っぽで何もない」と答えた。さらに「何もないというのなら、お前は何者だ」と聞くと「知らぬ」と答えた。武帝はこの答えを喜ばなかったので、達磨は北魏に向かったという。
この後、達磨は洛陽郊外の嵩山少林寺にこもり、壁に向かってひたすら坐り続けるという修行を9年間続けて、悟りに達したという伝説がある。この坐禅の姿を模して作ったのが、現在のだるまの玩具だ。あまりに長く座り続けたことによって、手足が腐ってしまった姿なのだともいう。達磨が行った「壁観(へきかん)」と呼ばれる修行法は、以後、禅というものの本質を表す礎となった。
少林寺に婆羅門僧(ばらもんそう)がいるという噂は中国の仏教者の間に広まった。だが、彼らが教えを求めて達磨のもとに行っても、ただ坐っているだけで、何も教えてくれない。その中で、慧可(えか)だけは、弟子となることを繰り返し志願した。沈黙して瞑想を続ける達磨は弟子を取るつもりはなく、これを拒否し続けた。ついに、慧可は自らの左ひじを切り落として、求道の決意を示したため、ようやく達磨も彼の入門を認めたという。この慧可が禅宗の第二祖となり、以後、中国に禅宗が広まったとされる。
達磨の入滅は、150歳という記録が残っているが、これは伝説として作られたものだろう。他宗派の僧侶に毒殺されたという説もある。遺体は熊耳山(ゆうじさん)に葬られた。
達磨は、釈迦の教えの本質をもう一度問い直し、「禅」という新しい流れを生み出した。中国で芽吹いた禅の教えにはどこかタオイズムに通じる質があり、仏教の中でも独特の位置にある。そして禅は日本に渡り、ミニマリズムを深化させ、結晶化した。達磨がなぜ東を目指したのか、そこには、大きな流れを受けた必然があったのかもしれない。